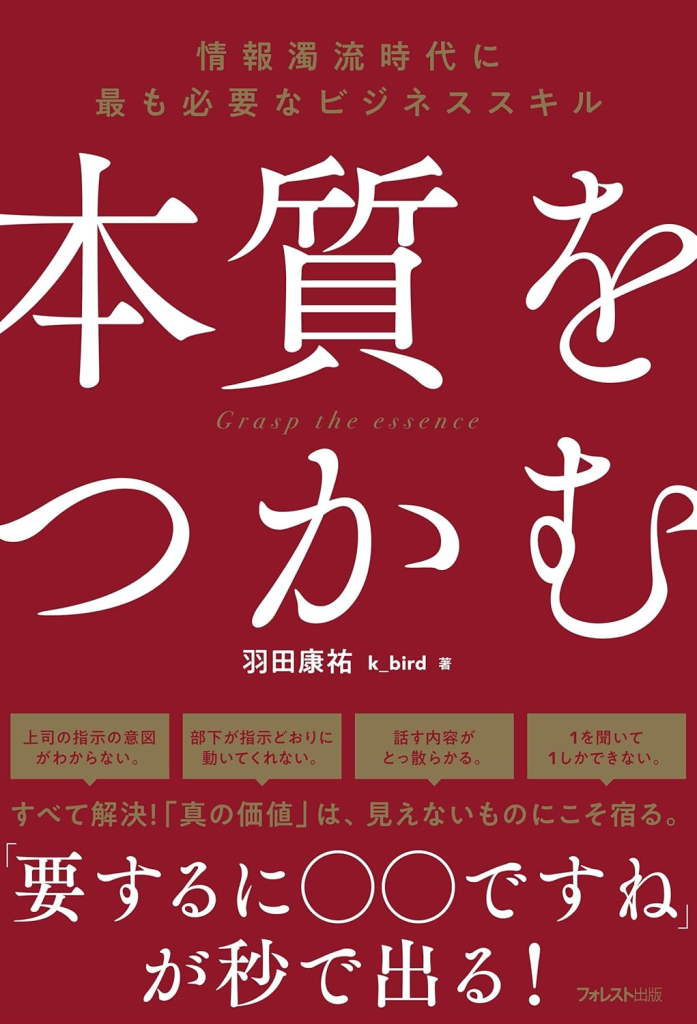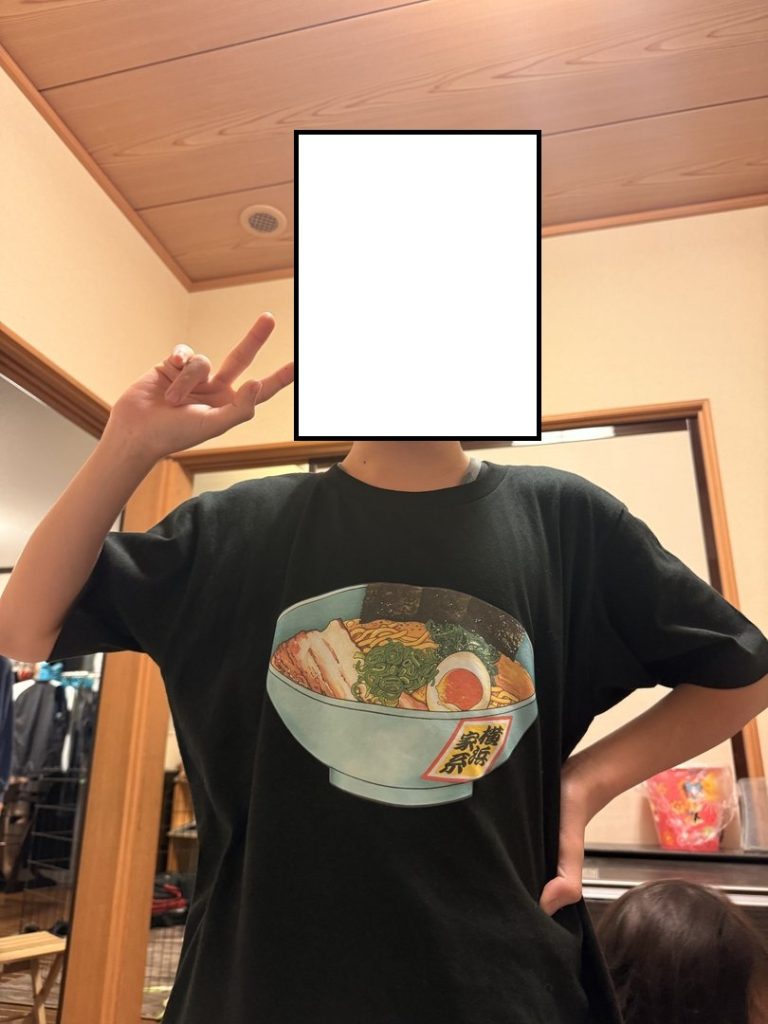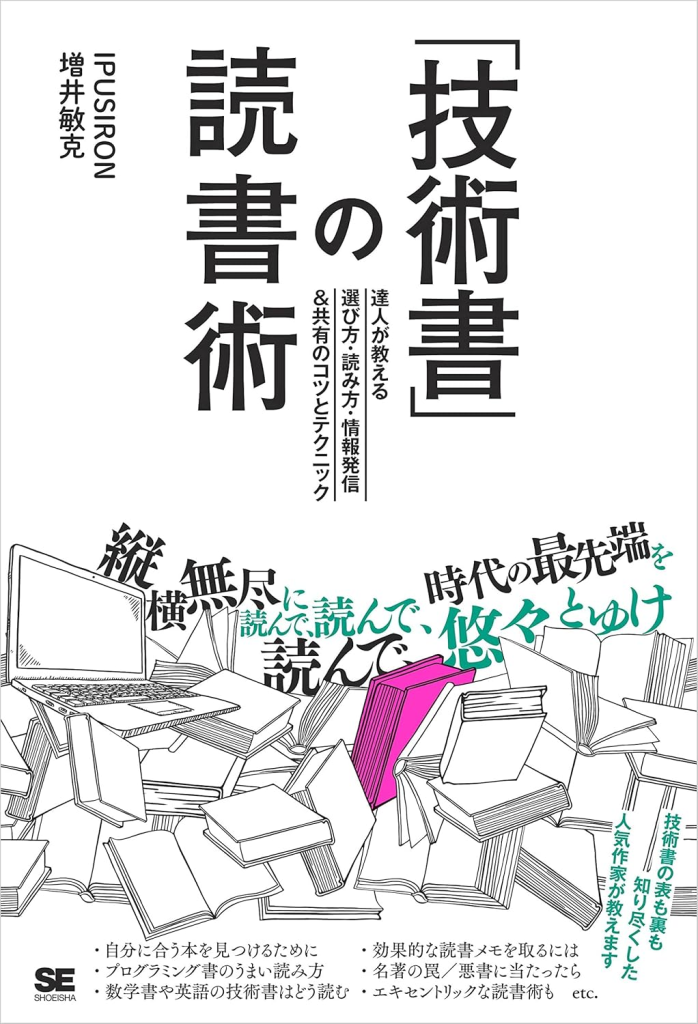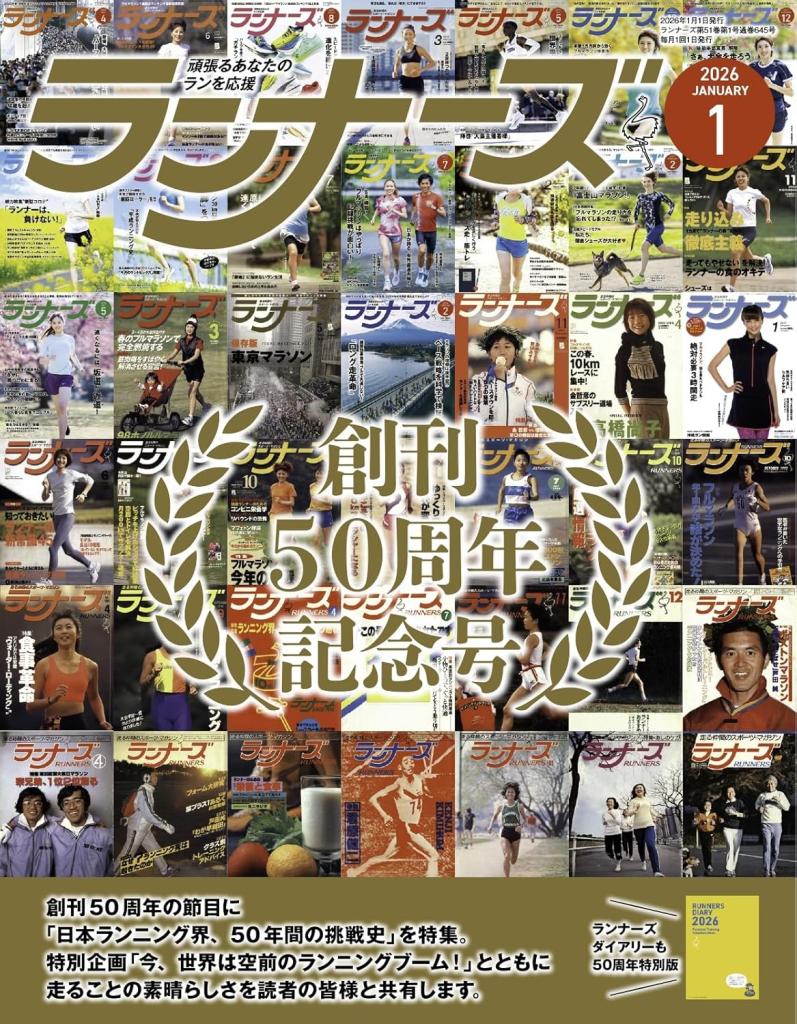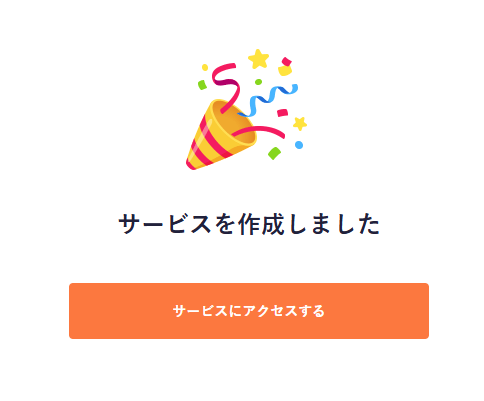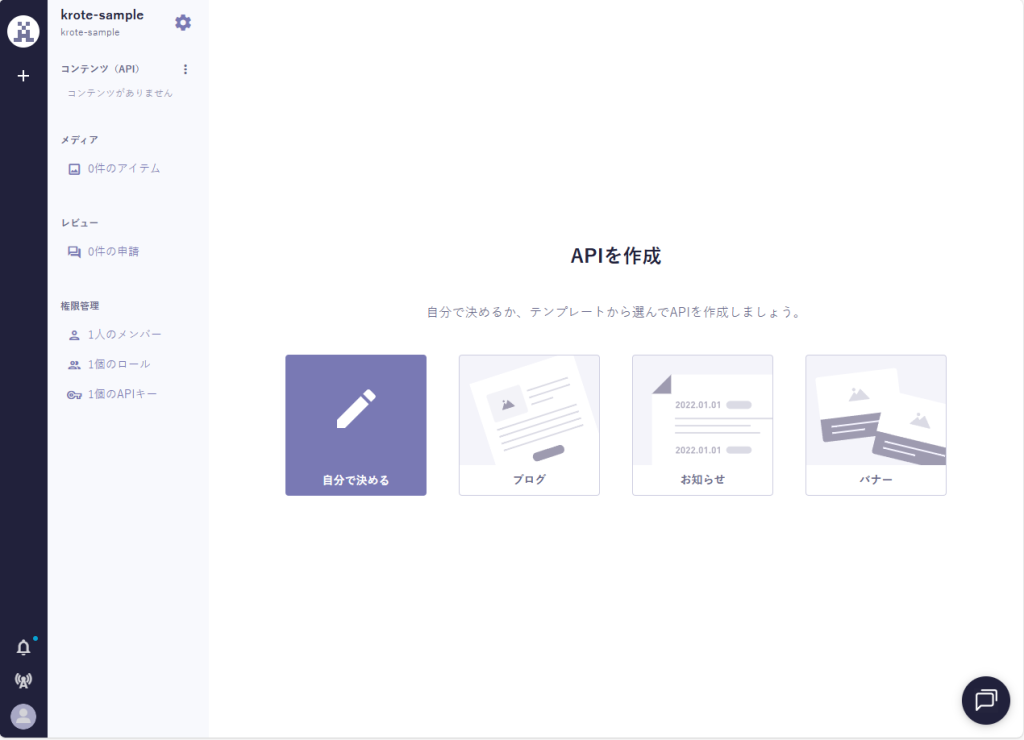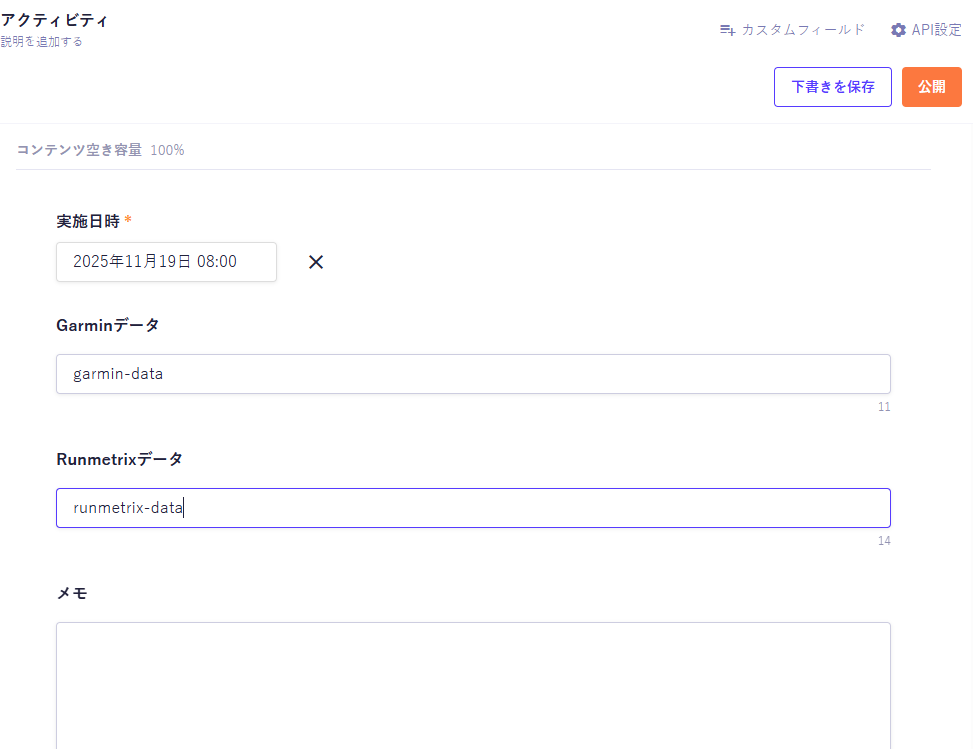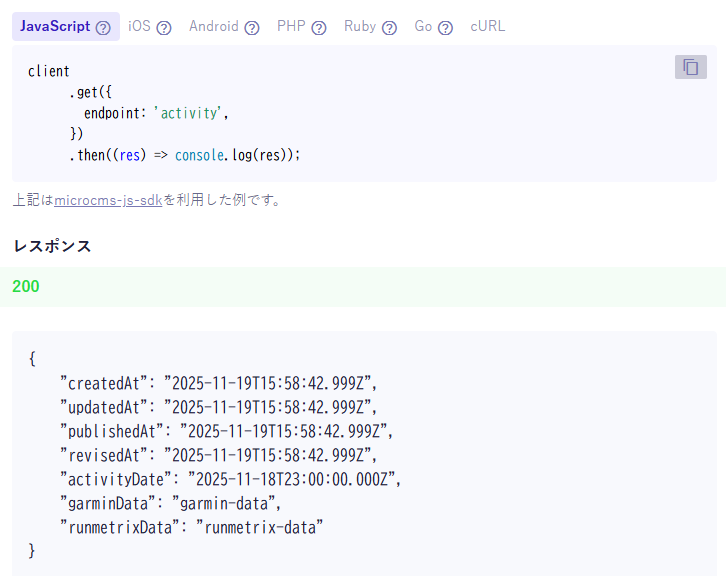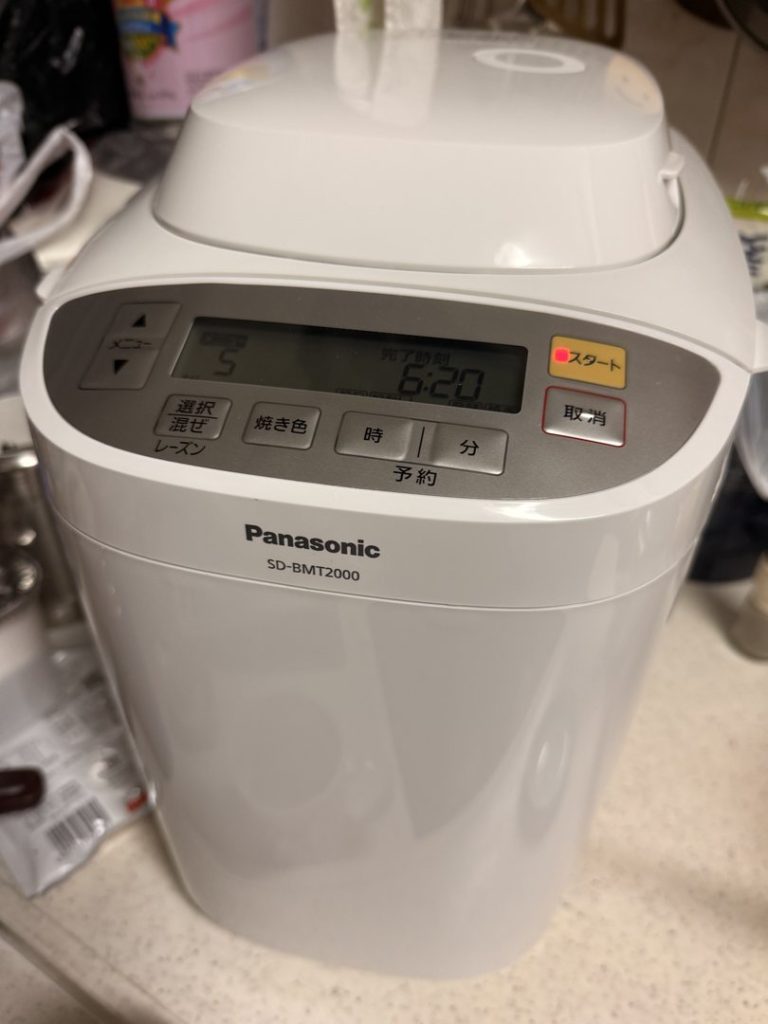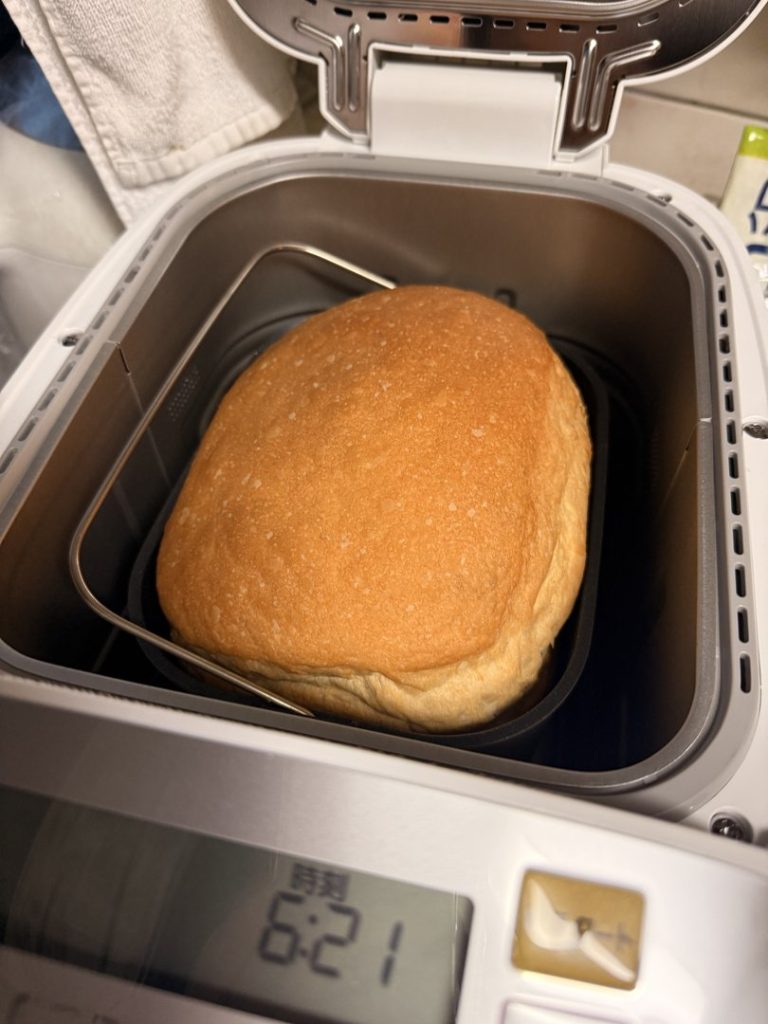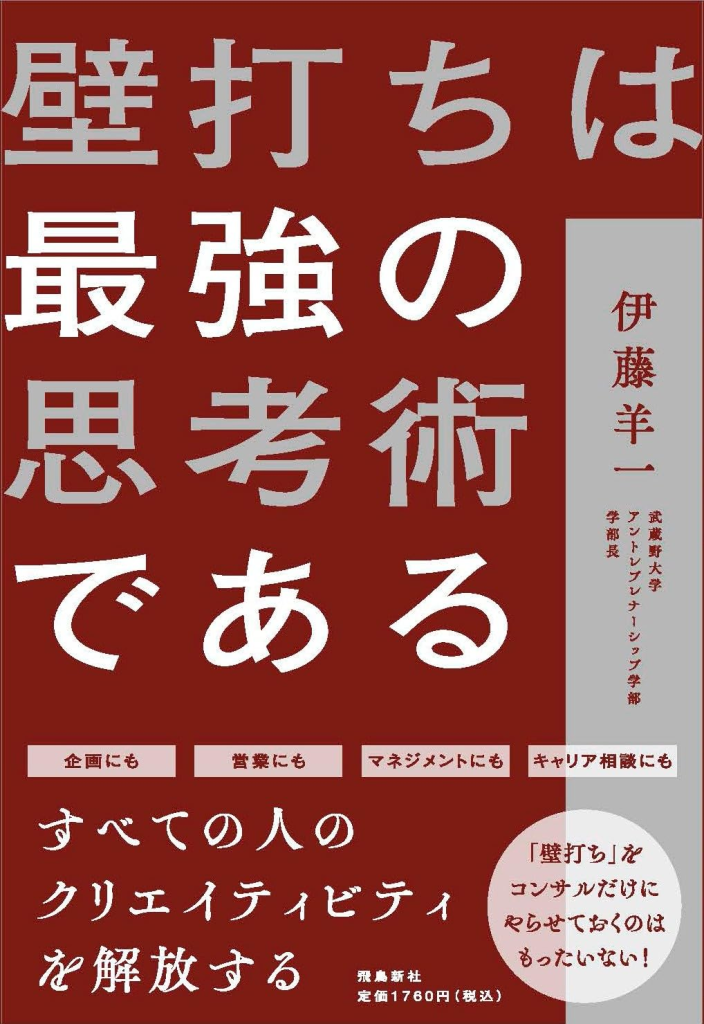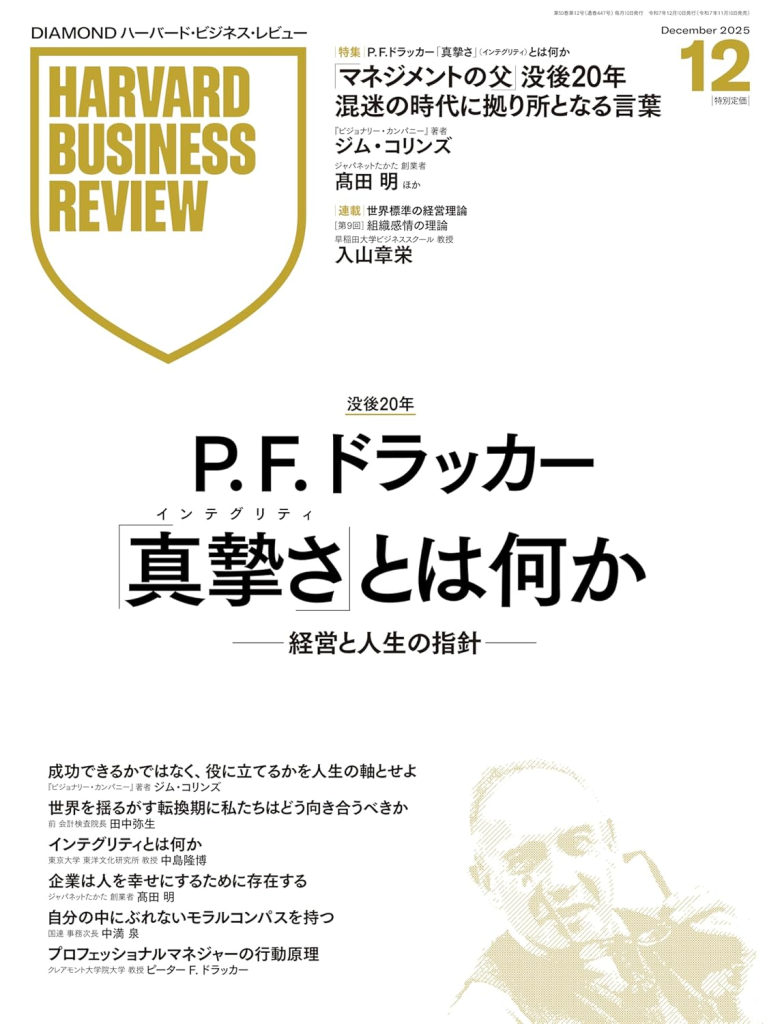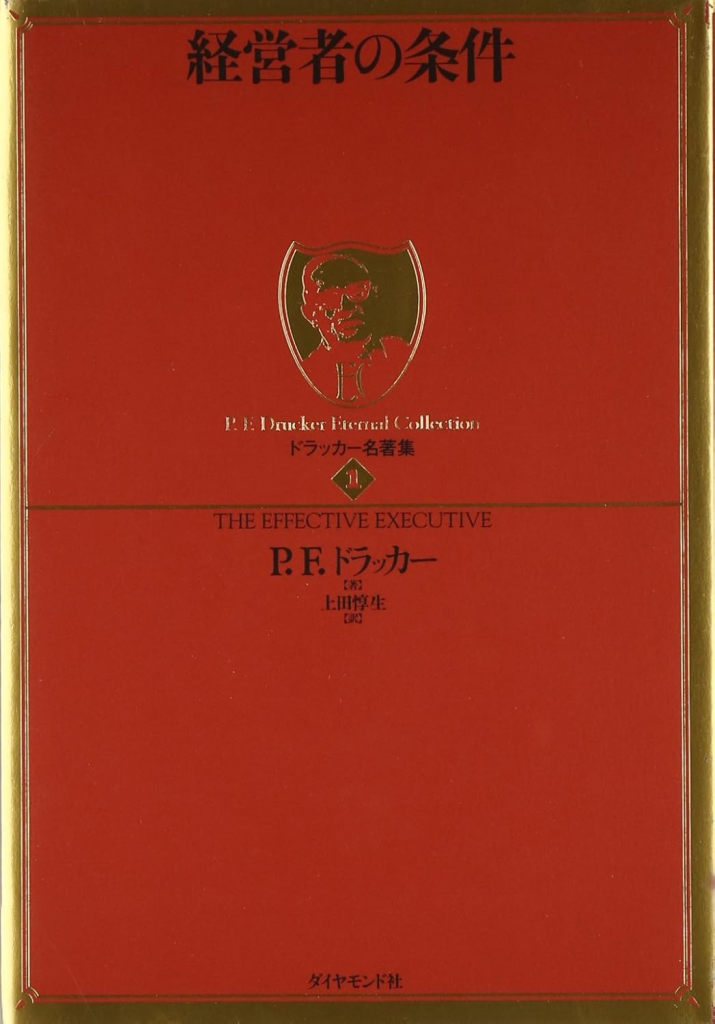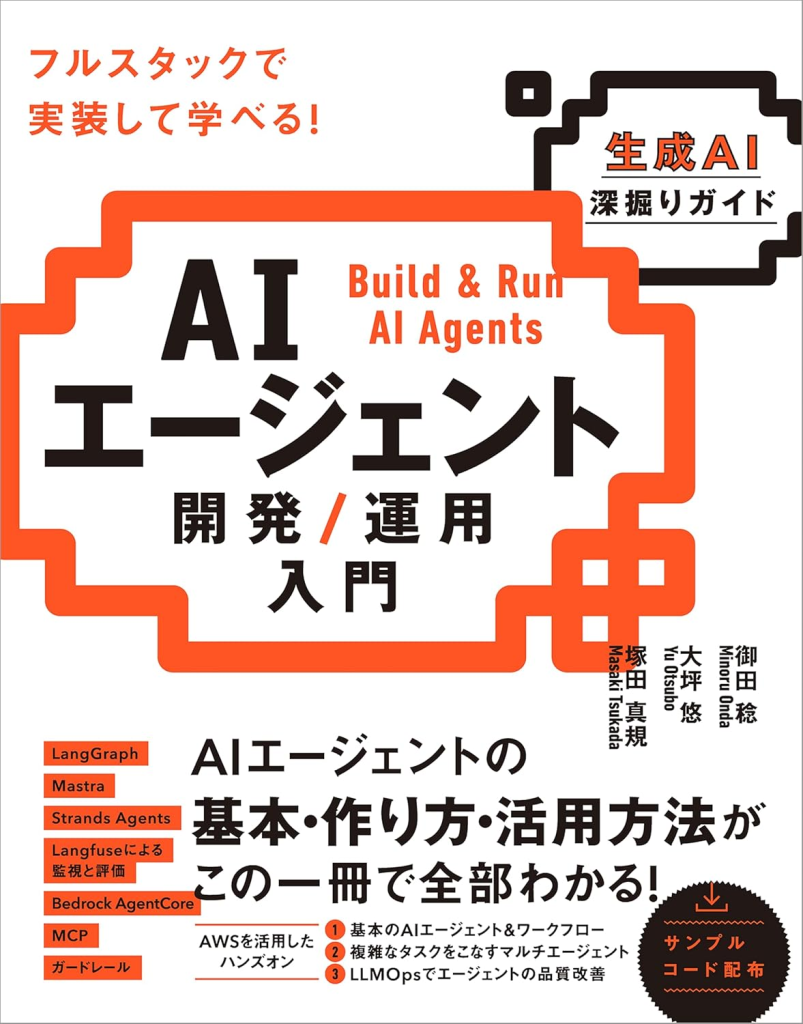先日公開された僕らの戦略論「出口の見えない“レベル上げ”から脱出!キャリアチェンジの戦略論」が面白かった
出口の見えない“レベル上げ”から脱出!キャリアチェンジの戦略… – ぼくらの戦略論 – Apple Podcast
IT技術者にしても、スキルアップに終わりなんか来ない。
そもそも、技術自体がどんどん新しいものが登場してくる中で、ひたすら新しいフレームワークや言語を学んだり、新しいプロジェクトにアサインされて1から覚えることが出来たりときりがない。
きりがないんだけど、結局のところそれを楽しむようなマゾ的な位置づけに陥ってしまいがちな感覚があった。
ポッドキャストで高宮さんが言っていた、「その頑張りの矢印が自分に向いているだけ」という言葉はその中でちょっとドキッとした。
何かしらの新しいプロジェクトで、自社や自分が何を手に入れるのか。
このプロジェクトを通してどう成長するのか?ということを第一に考えてしまうのはまさにこの”矢印が自分に向いている”状態になってしまっている。
本来あるべきは矢印の向きを「お客さんに向き合ってお客さんの価値を出す」という方向に向けていかないといけない。
”技術はあくまで手段”
これは、よくメンバーとの会話で出す言葉であるにも関わらず、いつの間にかスキルアップを目的化するような思考に陥ってしまっていたのではないか。
他社貢献や社会的な意義が見失われていないか?というと大仰に聞こえてしまうけれど、でも言ってしまえばそういうことなのだと思った。
うーん。
考えていることが自分事ばっかりだなぁ
反省です