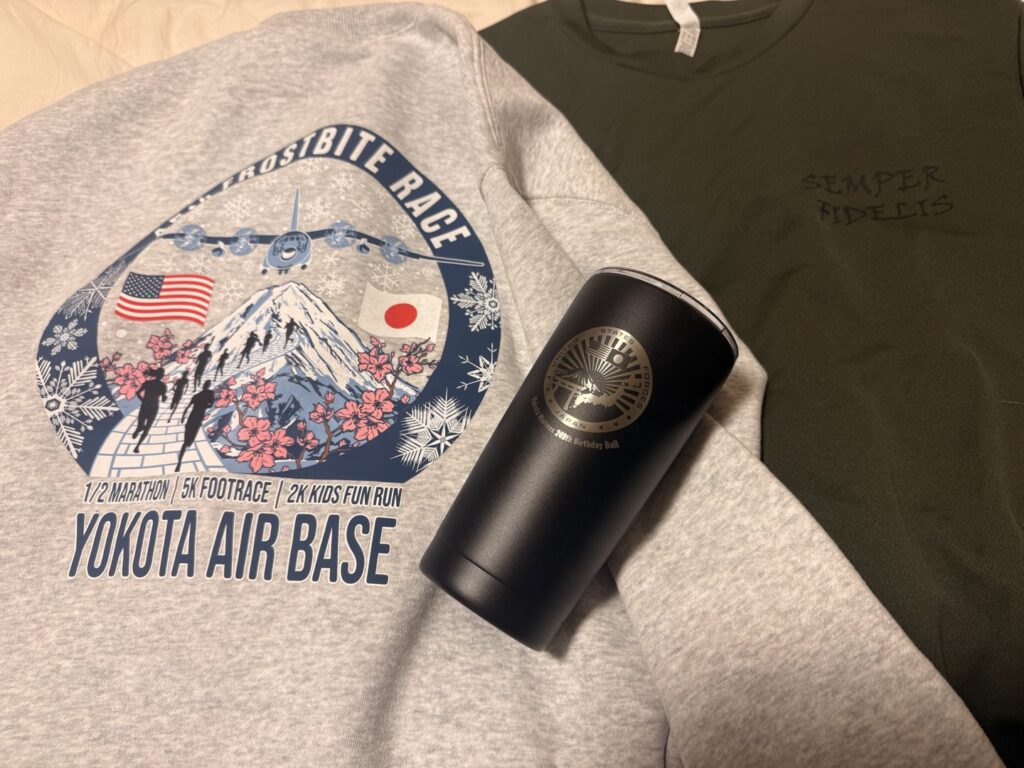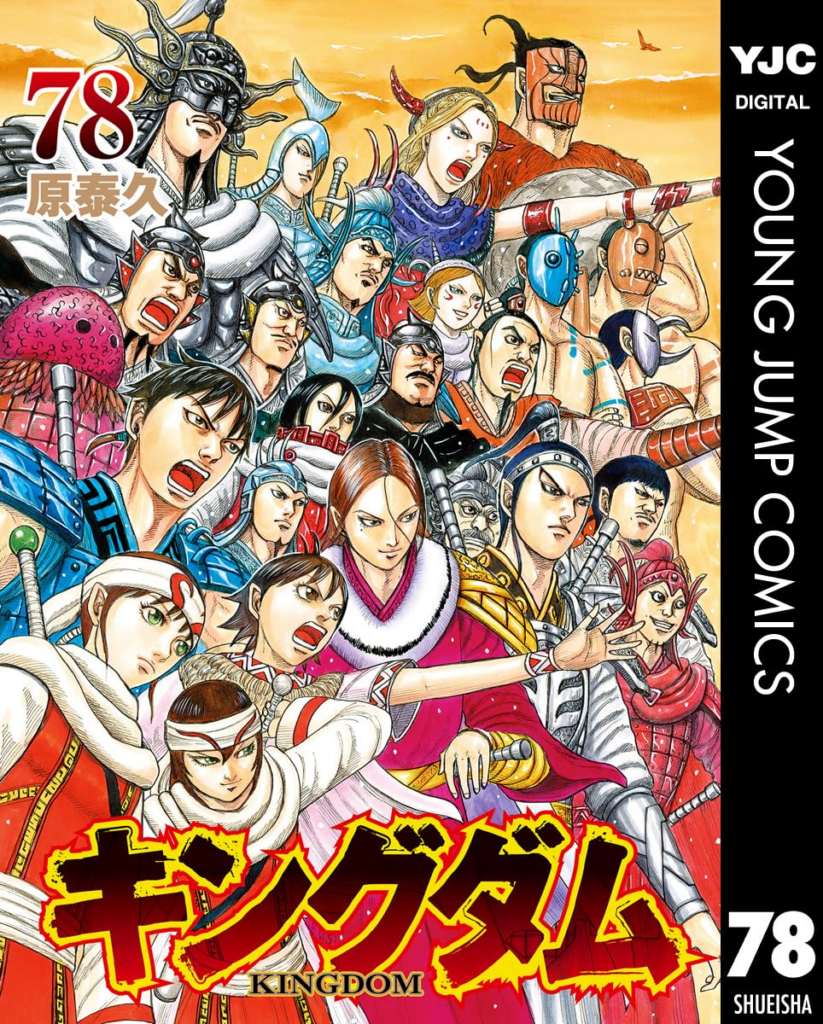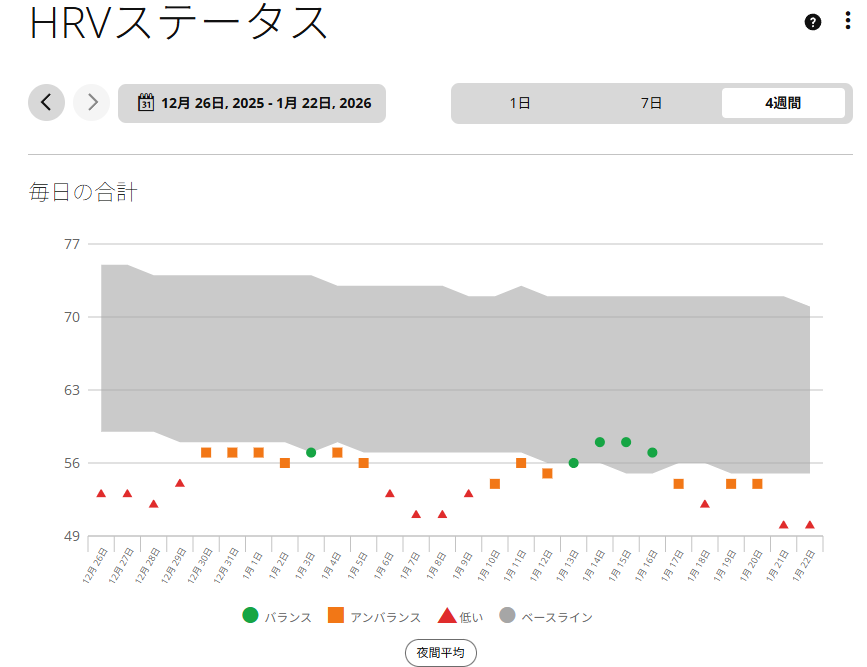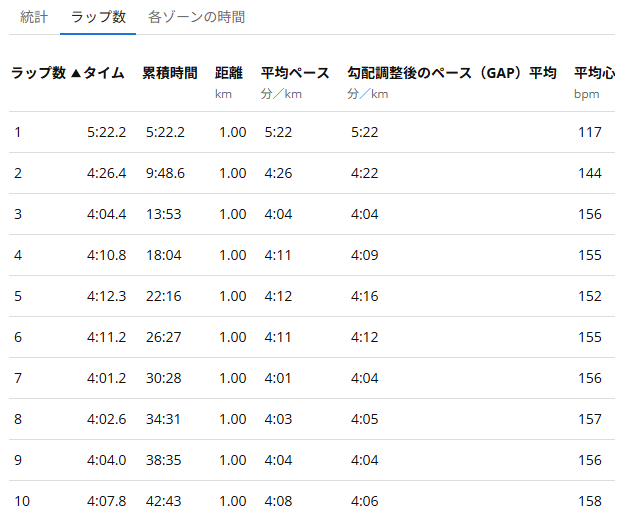Xを見ていたらこんな話が
日本3大湖マラソン🤝🏻完走キャンペーン!
— びわ湖マラソン【公式】 (@biwako2023st) January 26, 2026
びわ湖・かすみがうら・サロマ湖を完走で、
①特別メダル🎖️
②各地域のプチ特産品🎁
③3のゾロ目順位で他大会無料招待🏃
詳しくは大会HPの特設ページをチェック!https://t.co/vyygcImjb5#日本3大湖マラソン pic.twitter.com/3V7Omoc3sD
ハーフマラソンのジャパンプレミアムハーフといい、複数の大会で共同企画する動きが流行ってきているんでしょうか。
というより、マラソンブームで調子に乗ってあちこちで大会を作ったはいいものの、作りすぎて人が集まらなくなっているのでしょうか。。。
いずれにしても気になるところです。
琵琶湖マラソンのページにも書かれていますが、2026年の開催日は以下のようです
- びわ湖マラソン3月8日(日)(例年3月第2週の日曜日)
- かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン4月19日(日)(例年4月第3週の日曜日)
- サロマ湖100kmウルトラマラソン6月28日(日)(例年6月最終週の日曜日)
びわ湖マラソンはすでにエントリー終了済み。
かすみがうらマラソンは通常エントリーが締め切り済みで料金加算のレイトエントリーが残っている。
そして、サロマ湖100㎞は。。。。なんと今日(1/26)からエントリー開始!!
うーん、サロマ。いいですね。。。
行きたいのはやまやまなのですが、今年はチャレンジ富士五湖も出ることを考えると、年1回程度と考えている宿泊RUNは、家族巻き込まないとって思ってしまいます。
いっそのこと北海道旅行を企画したほうがいいような気もしますが、開催予定の6/28は夏休みでも何でもない普通の週末なんですよね。
子供を連れていくのはまず無理です。
やるのであれば、びわ湖、かすみがうらを走ってから集大成としてサロマという流れが美しそう。そう考えると2027年に挑戦かな?
いずれにしても、いろいろな企画を立ててくれるのは楽しみが増していいですね。