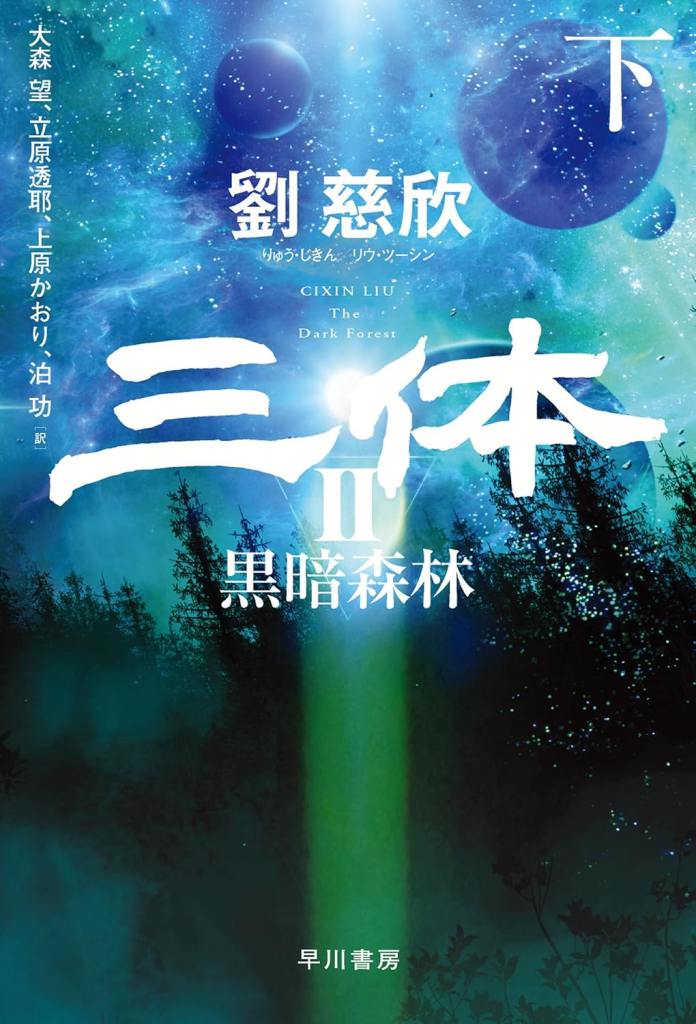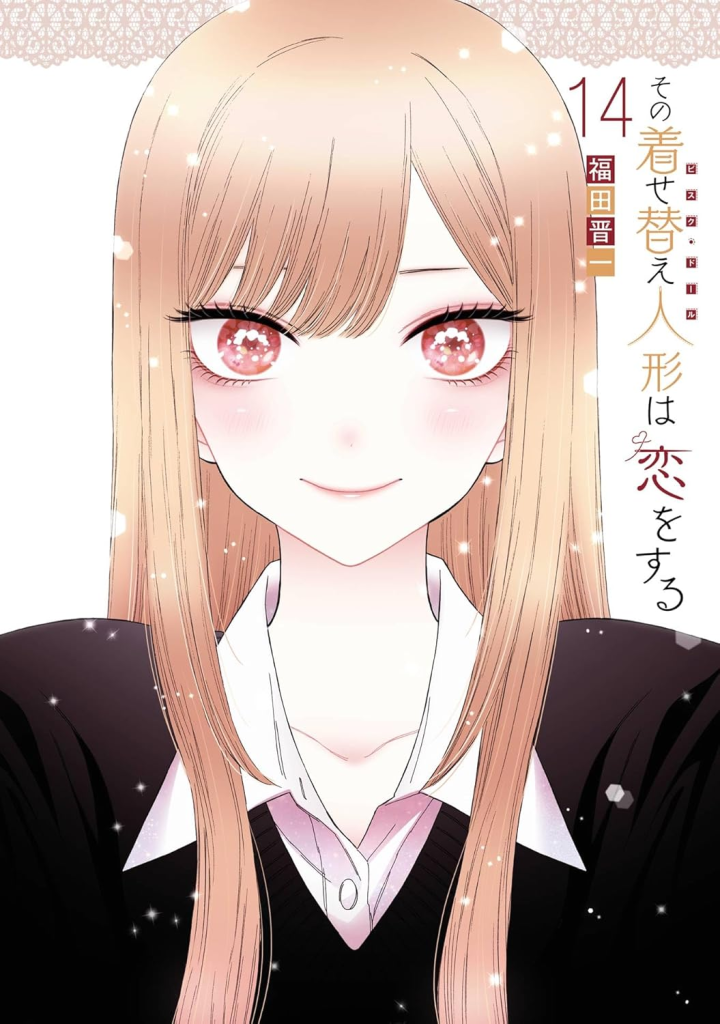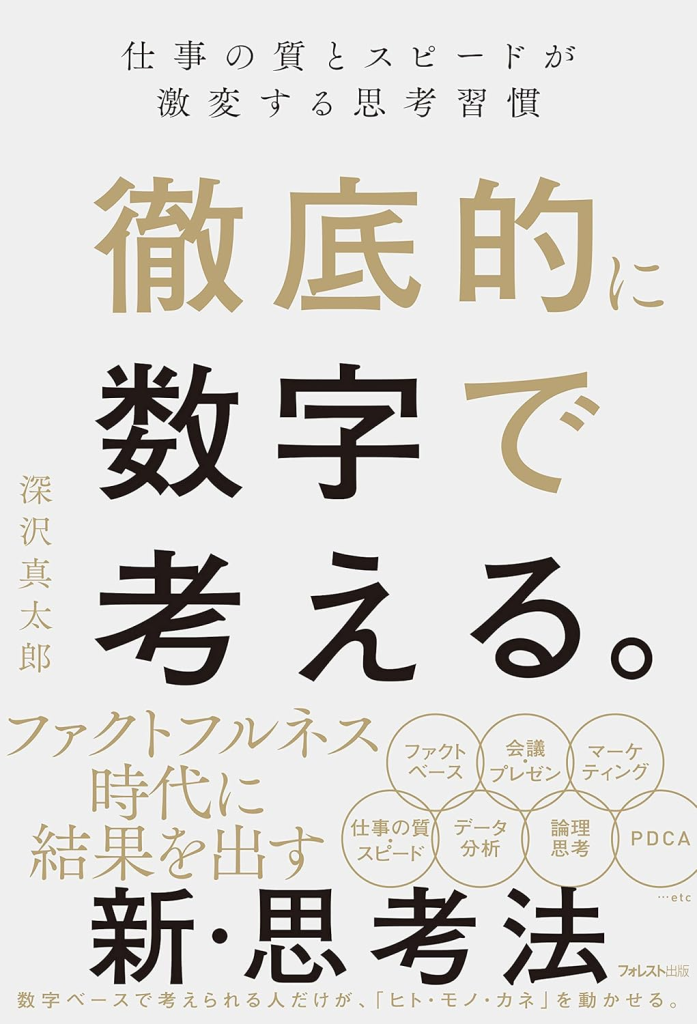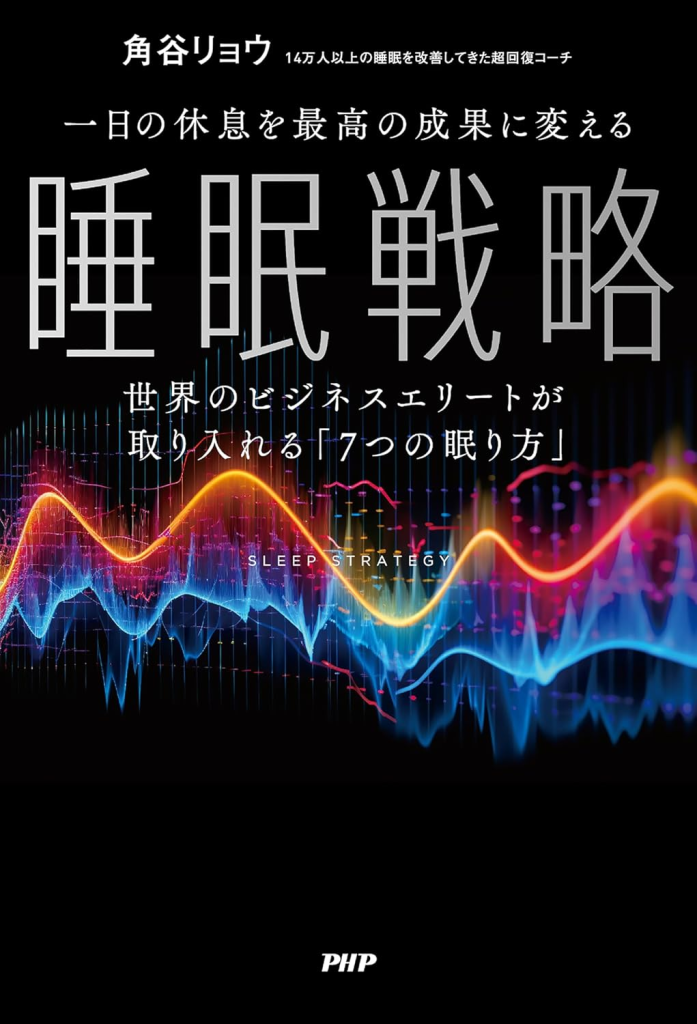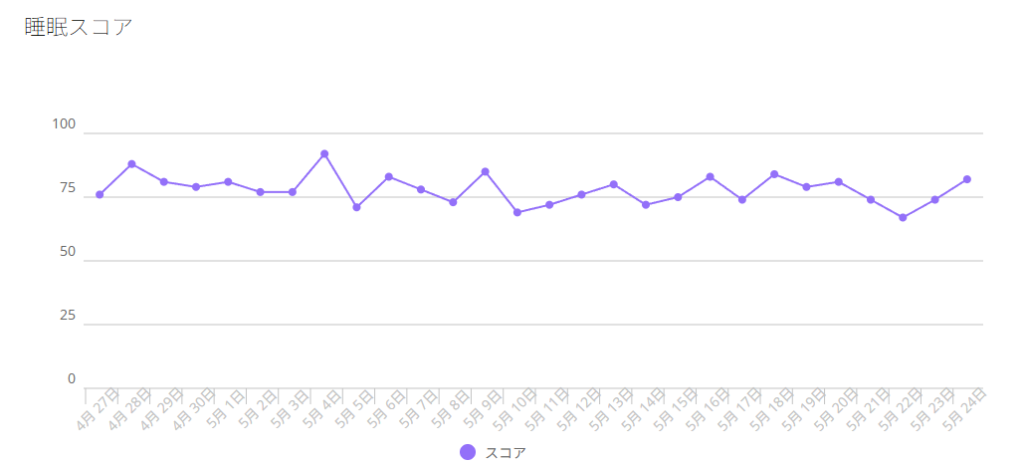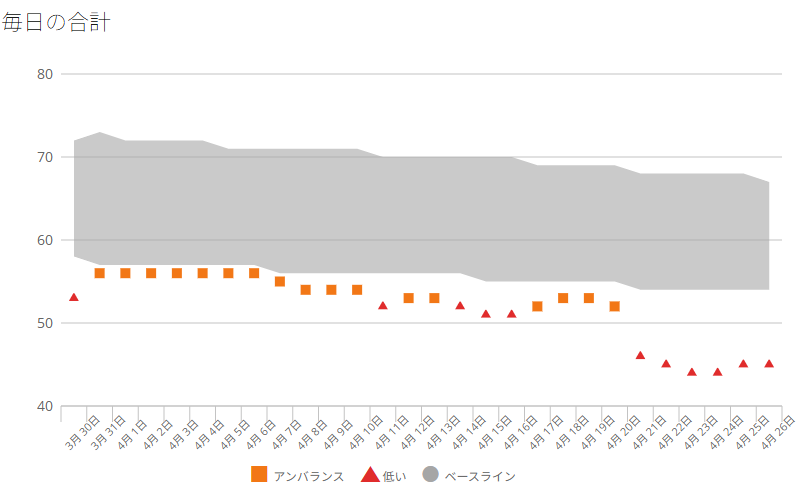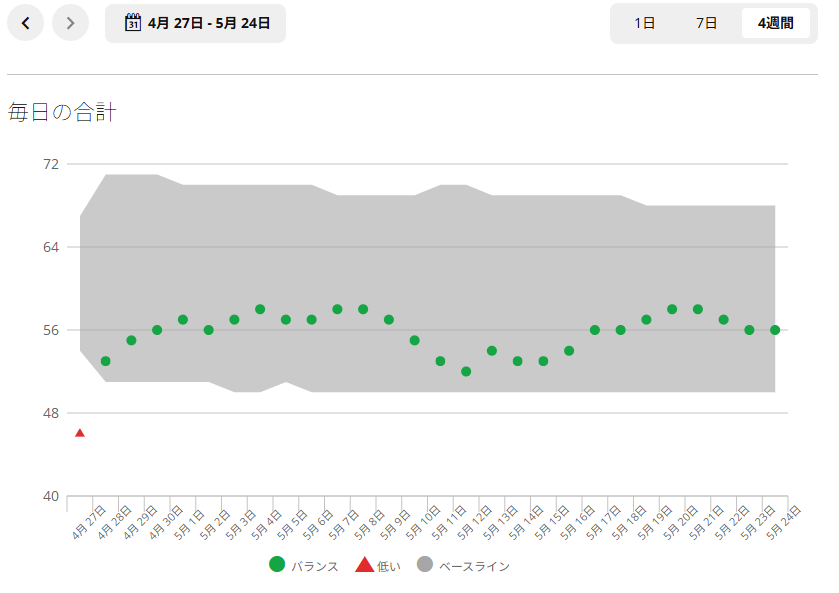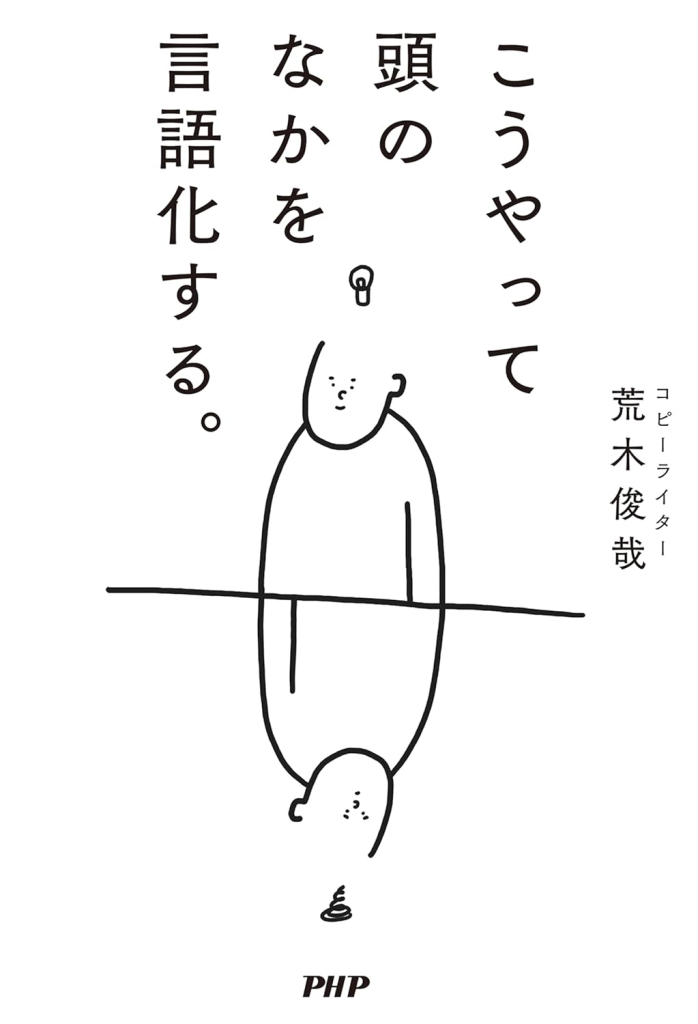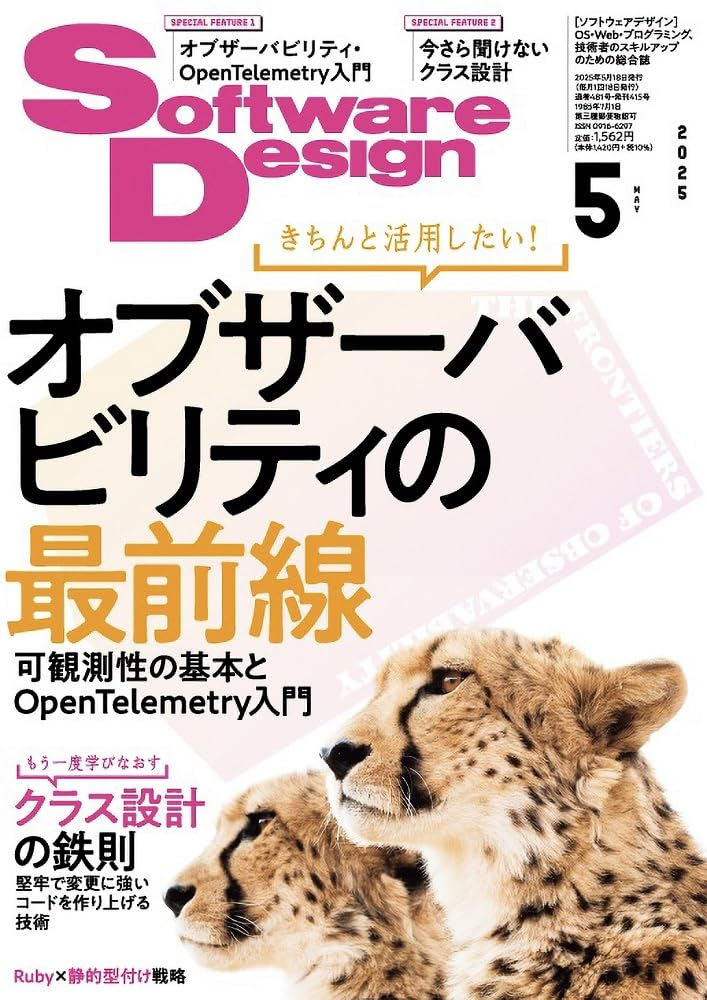Audibleにあったので手にとって見た
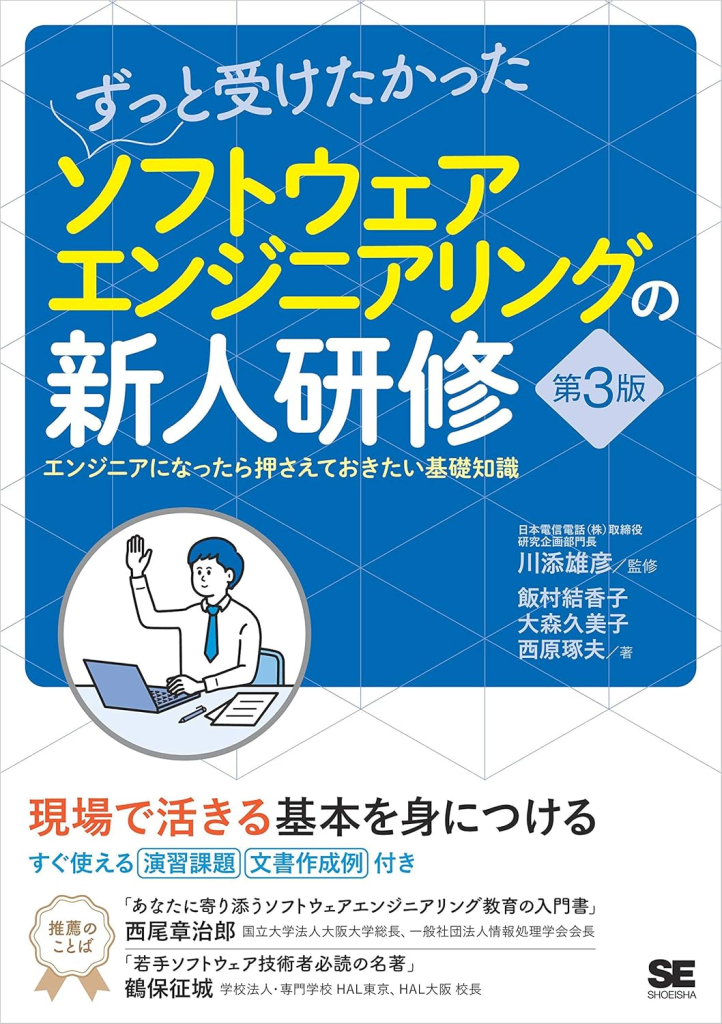
ずっと受けたかったソフトウェアエンジニアリングの新人研修 第3版 エンジニアになったら押さえておきたい基礎知識
私自身、大学時代は情報系の学科を出たわけではなかったので、社会人になってからプログラミングを始めた口。
最初は周りとの差に苦労をしました。
自分自身がどういう新人研修を受けたかな?というと、社会人研修は受けたものの、ITの新人研修は入った会社には存在しませんでした。
配属された部署は、新人は私一人で他に開発をする人は二人だけ。そういう規模の部署だったので、新人研修なんてものがないんですよね。
しばらくは書籍をひたすら読んで学ぶということをしていた記憶があります。
(その後、集合研修みたいな形の体制に徐々に変わっていきましたが)
現在の会社でも今年の新人さんたちは新人研修を現在行っていて、7月から現場配属。
配属後は各現場での学習と実務が待っているわけです。
新人研修でどれくらい、何をやるのか?はぶっちゃけ会社によってものすごい違うと思います。
そもそも、どのレベルの新人が入ってくるのかが一番大きな落差が生じる部分だと思いますし、新人研修でどこまでのレベルに到達することを目指すのか?も大きく違いそうです。
自社のプロダクトやパッケージを持っている企業であればその技術スタックを中心とした研修になると思いますし、SESなどを展開している場合はJavaなど比較的ヒット率の高い技術を教える形なんだろうと思います。
本書では、それら技術に特化した研修ではなく、もっと一般的な。
ソフトウェア開発って何をするものなの?ということに重点を置いた教育になっています。
いわば、基本情報技術者試験的な感じがしました。
結構前まではこの辺の知識ってそれほど必要性を感じていなかったんですよね。
でも最近、文系出身だとかいろいろな新卒が入ってくる中で、このあたりの知識がないと共通言語がなくて会話が成り立たないな、と感じるようになってきました。
そういう意味では悪くはないのですが、これで新人研修を終えられると現場は大混乱するだろうなぁと思うのも事実。
何を持って新人研修を終えたとするのか。どこまでのラインまで行くことを目指すのかという、新人研修の要件があまりにも企業の余裕だとかによって変わっている現実がなんともしがたい、歯がゆさを残します。
結局、自社なりの教育カリキュラムを作るしかないようにも。
なんとも非効率な効率性ですね
この業界に絶望した!