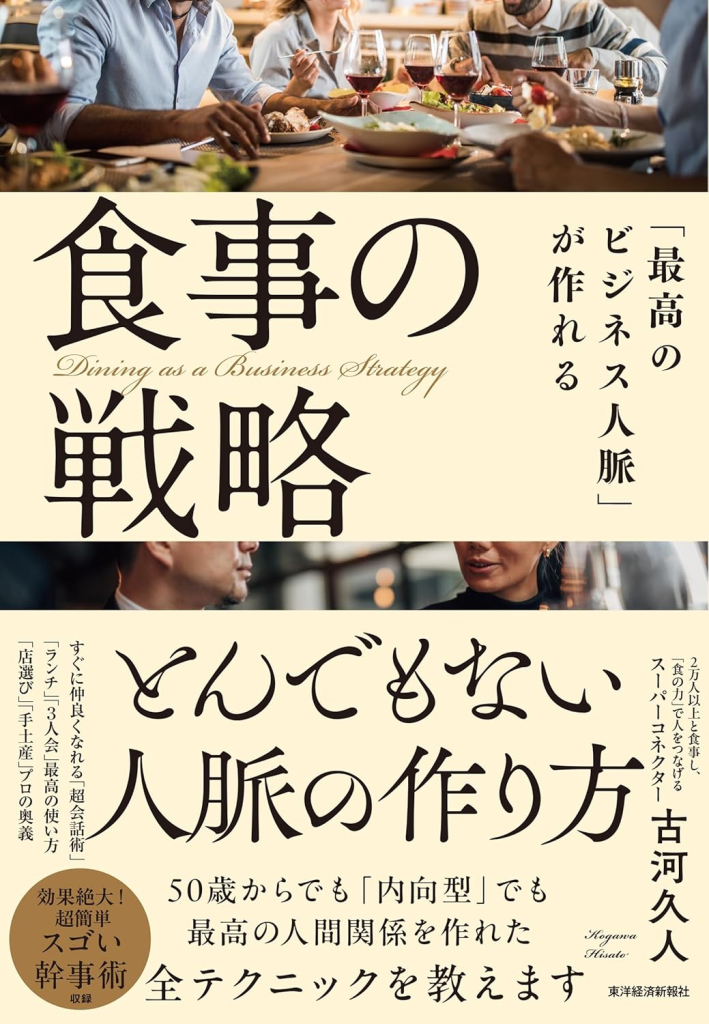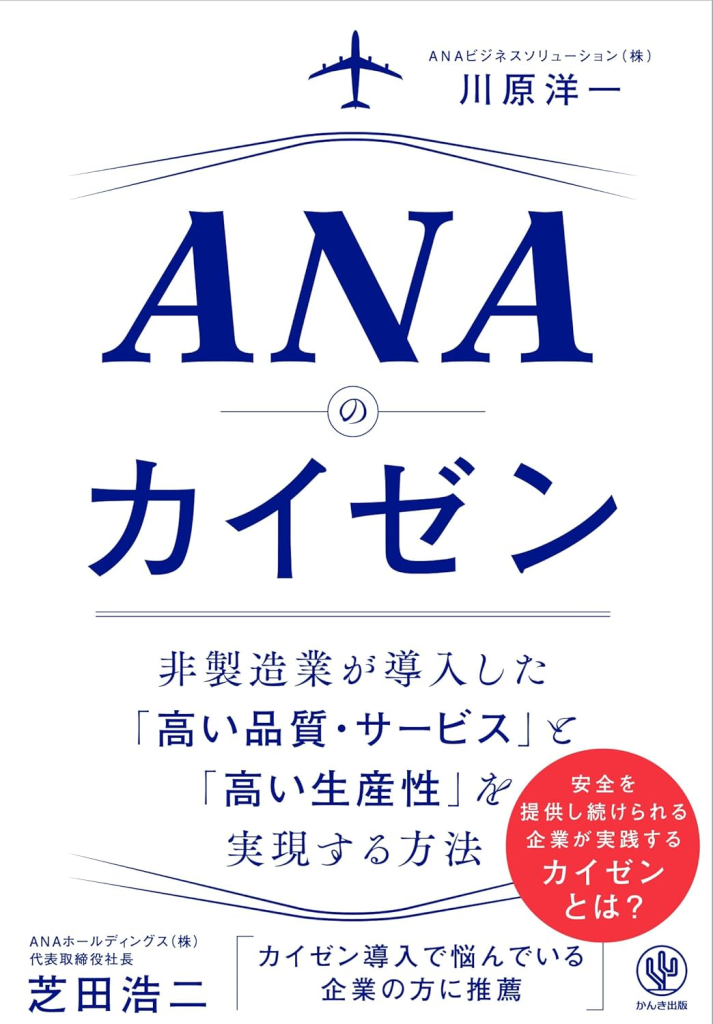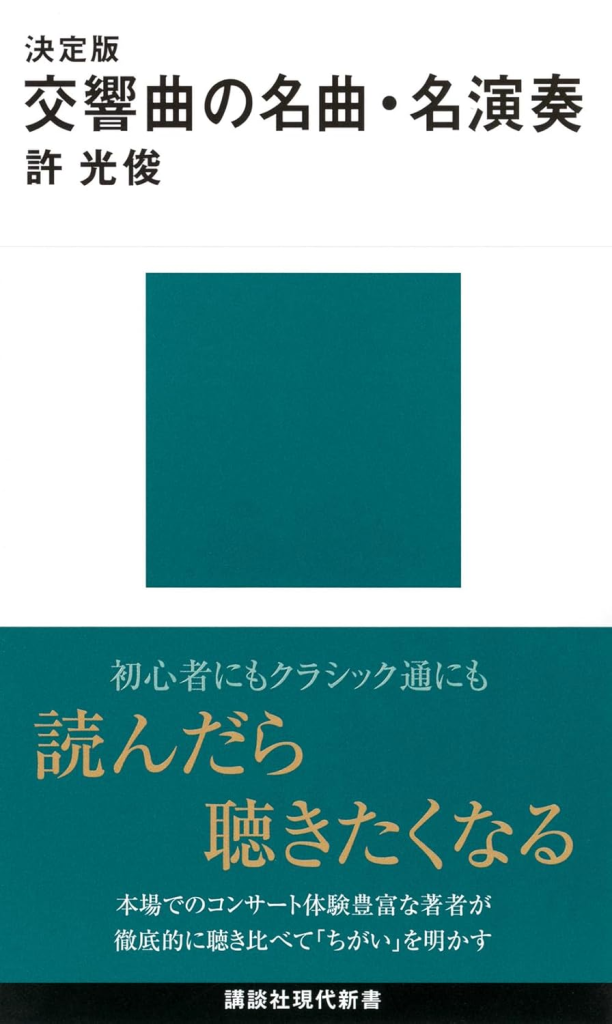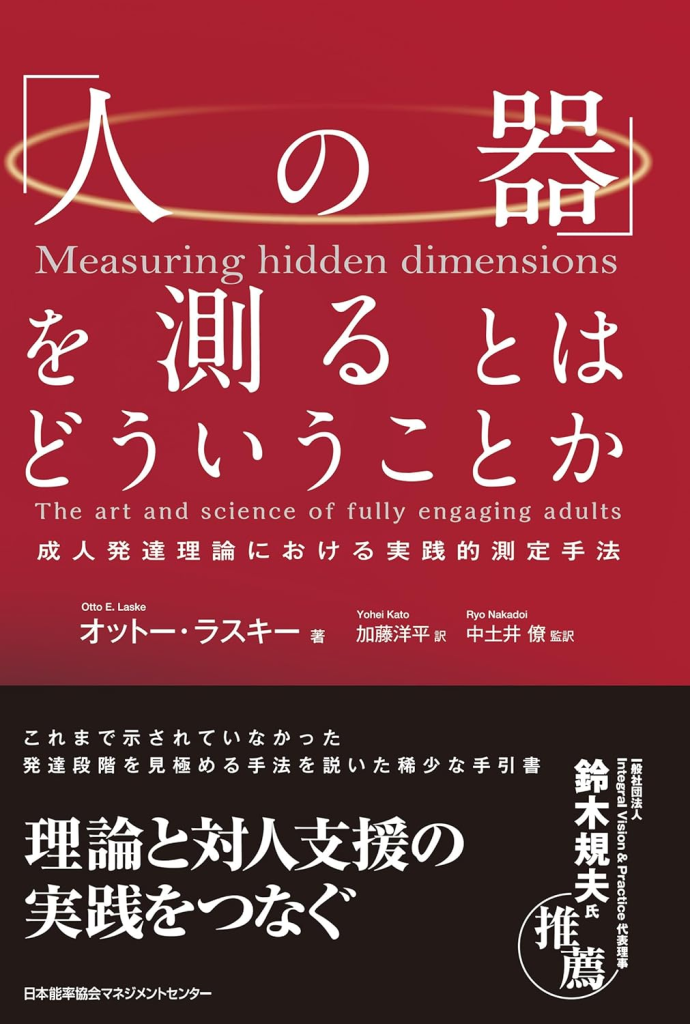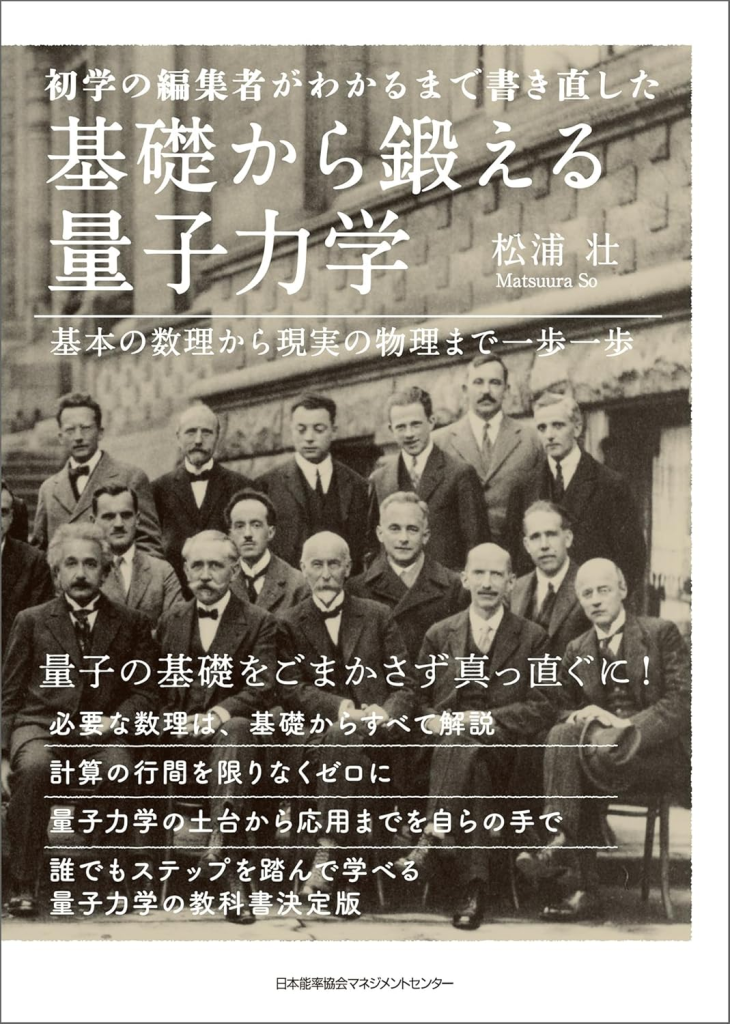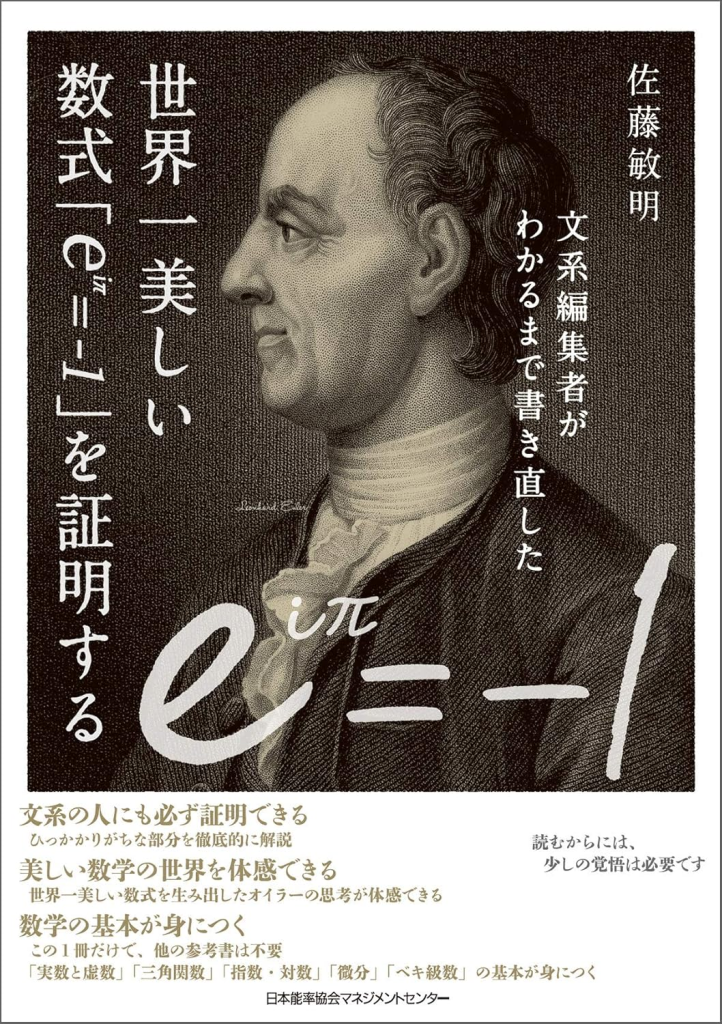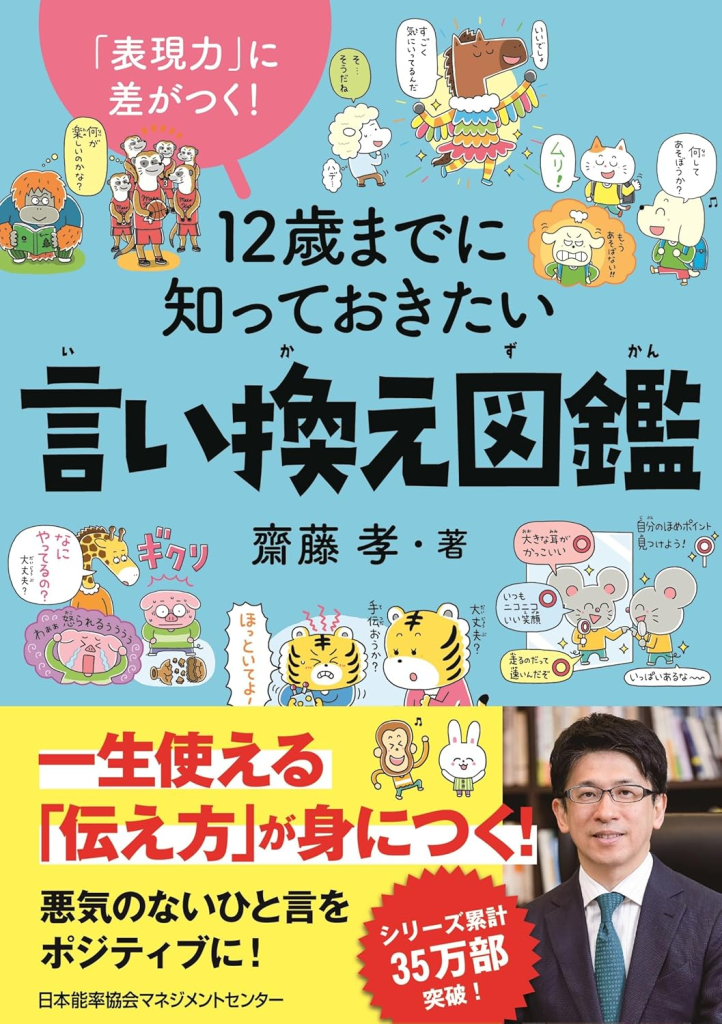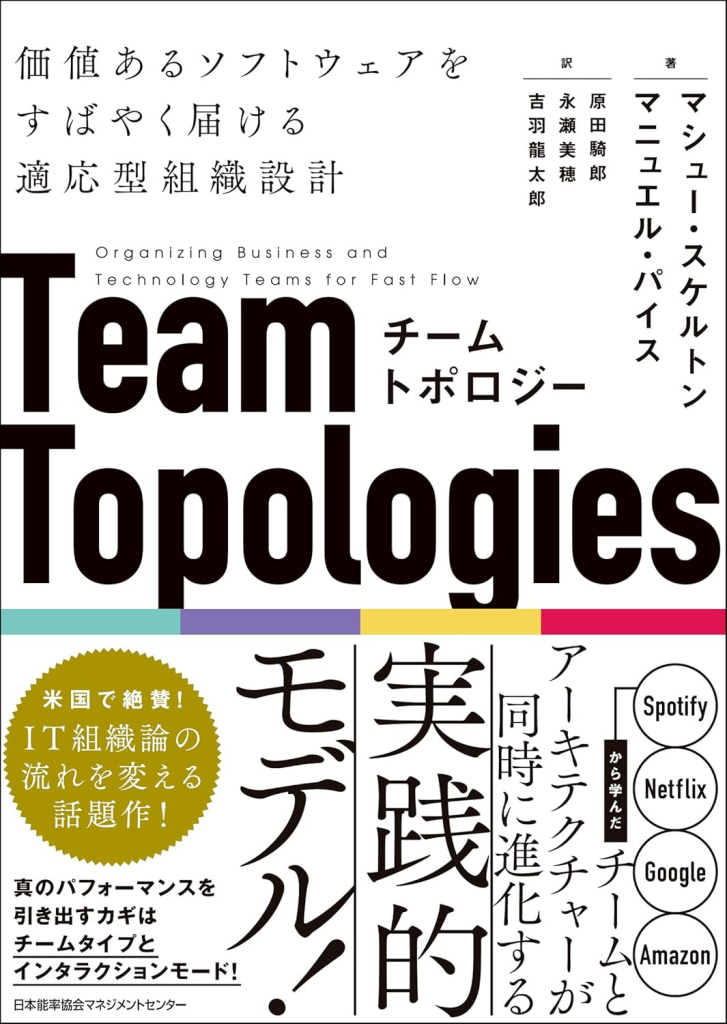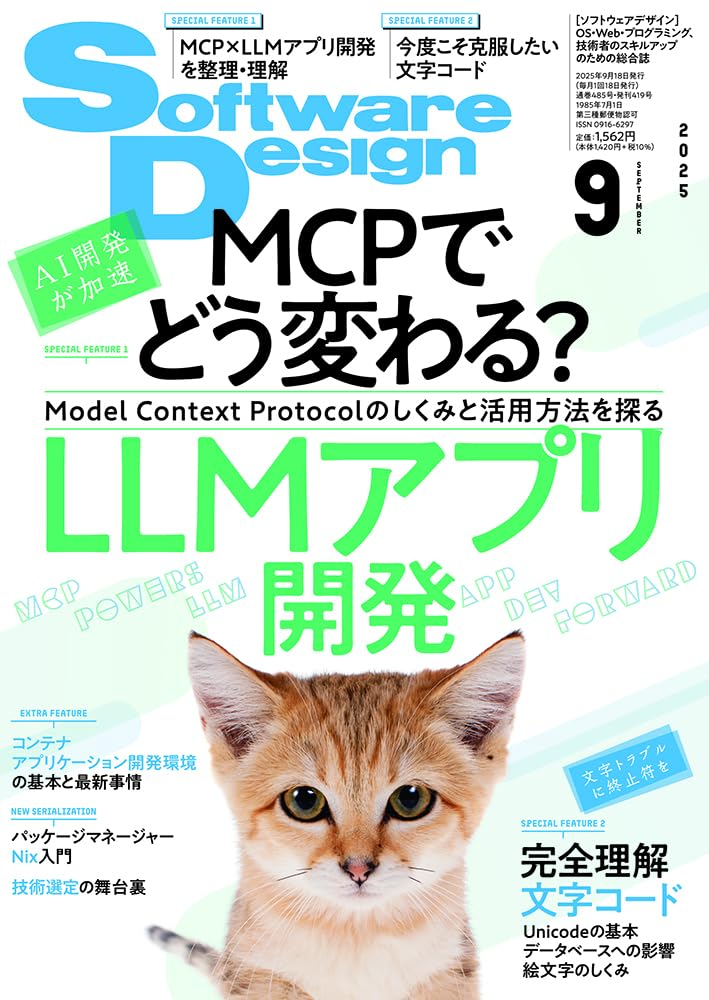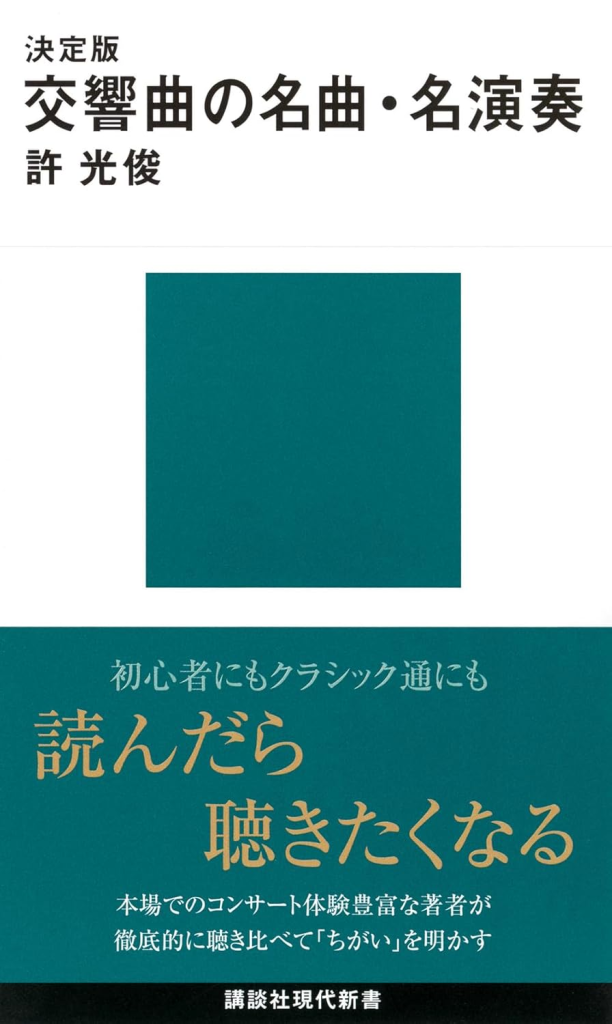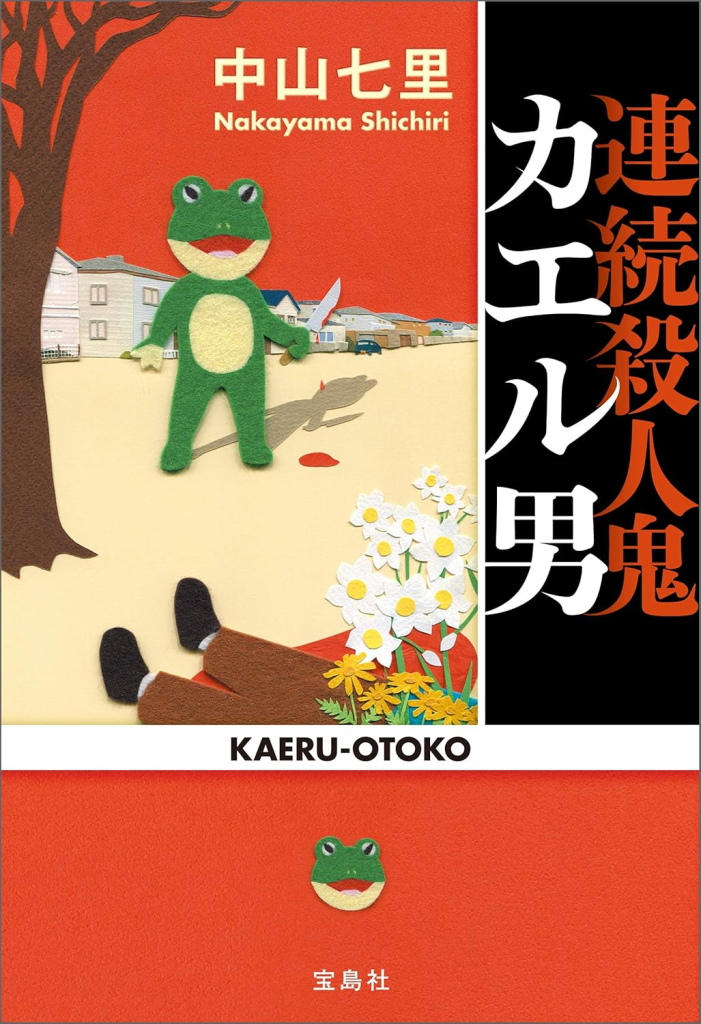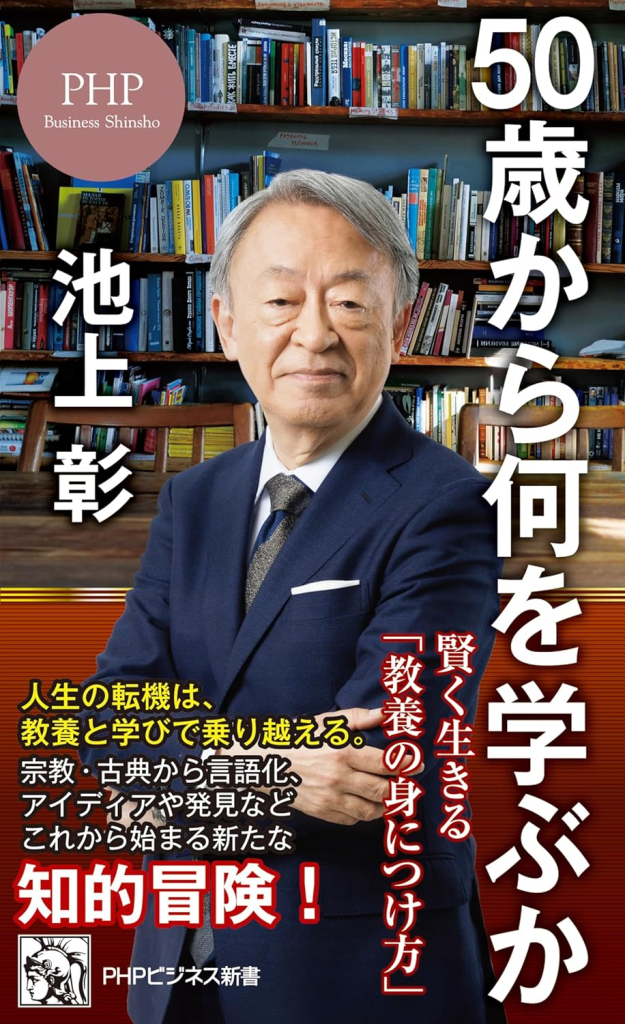AmazonでKindle本199円キャンペーンがやっていた
https://amzn.to/4nc4RfF
199円ということで、ちょっと積読状態になってしまう可能性も高いんだけど、気軽にポチポチっといくつかしておいた。
「人の器」を測るとはどういうことか 成人発達理論における実践的測定手法
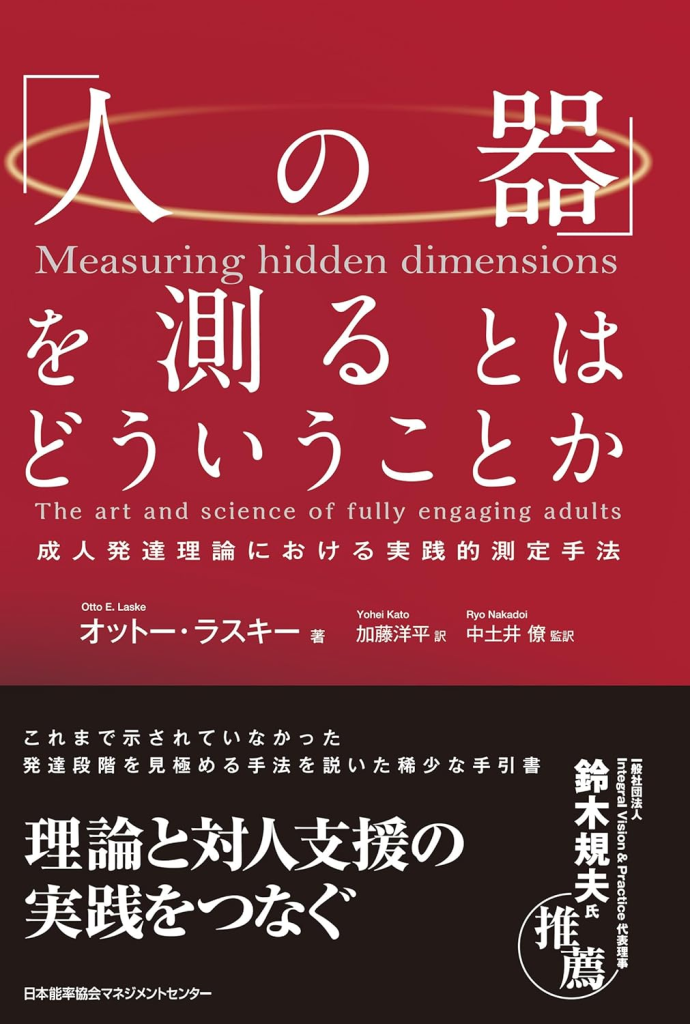
「人の器」を測るとはどういうことか 成人発達理論における実践的測定手法
いや、人の器ってどういうことよ?とタイトルでポチった。
しかも、器を大きくするとかそういうことではなく、測るという。
概要としては、”成人発達理論”というものらしいが、名前だけ聞くとさっぱりだ。
まぁ、読んでみることにしようかと。
初学の編集者がわかるまで書き直した 基礎から鍛える量子力学 基本の数理から現実の物理まで一歩一歩
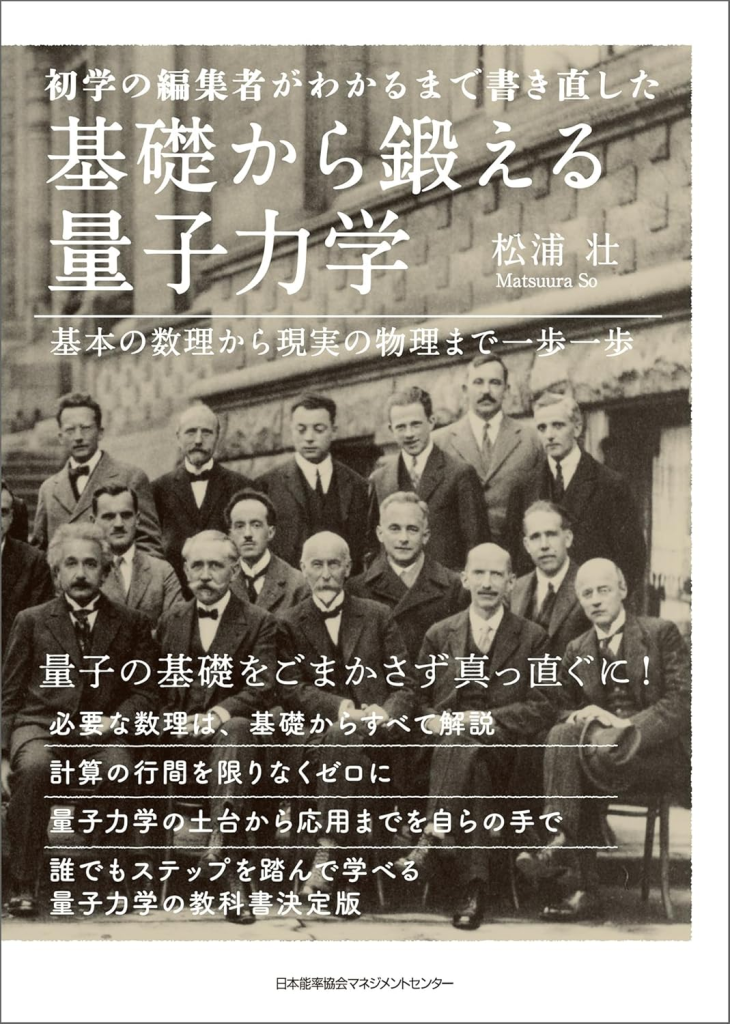
初学の編集者がわかるまで書き直した 基礎から鍛える量子力学 基本の数理から現実の物理まで一歩一歩
何度聞いても、「それってどういうこと?」「それ何が嬉しいの?」となってしまう量子力学。
これを知っていようがいまいが、そんなにこれから先変わるかな?はあるんだけど、どうせこれからの人生で何度となく「量子コンピュータって何」って質問は耳にすることになるだろう。
本当に理解できるのかは甚だ疑問ではあるけれど、手にとって見ることにする
文系編集者がわかるまで書き直した世界一美しい数式「eiπ=-1」を証明する
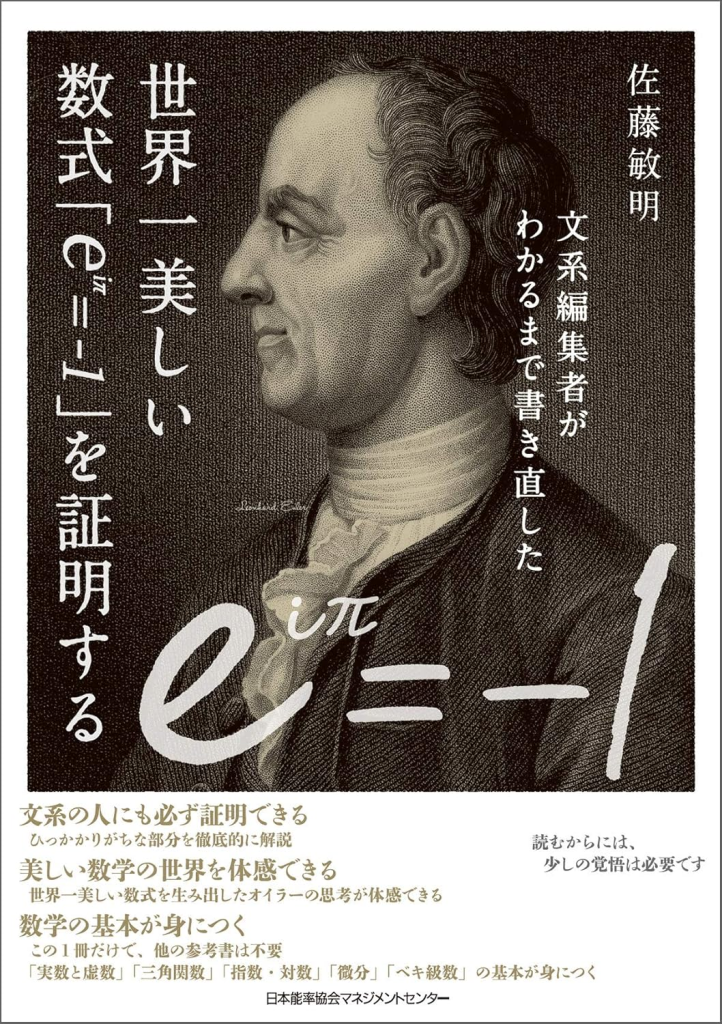
文系編集者がわかるまで書き直した世界一美しい数式「eiπ=-1」を証明する
正直、なんでポチってしまったのかがわからない。
わからないけれど、なんか知っていると凄いかも?という、甚だ頭の悪い感じの理由でポチったんだと思う。
もはや、こんなこと書いている時点で理解できるとは思えない
「表現力」に差がつく! 12歳までに知っておきたい言い換え図鑑
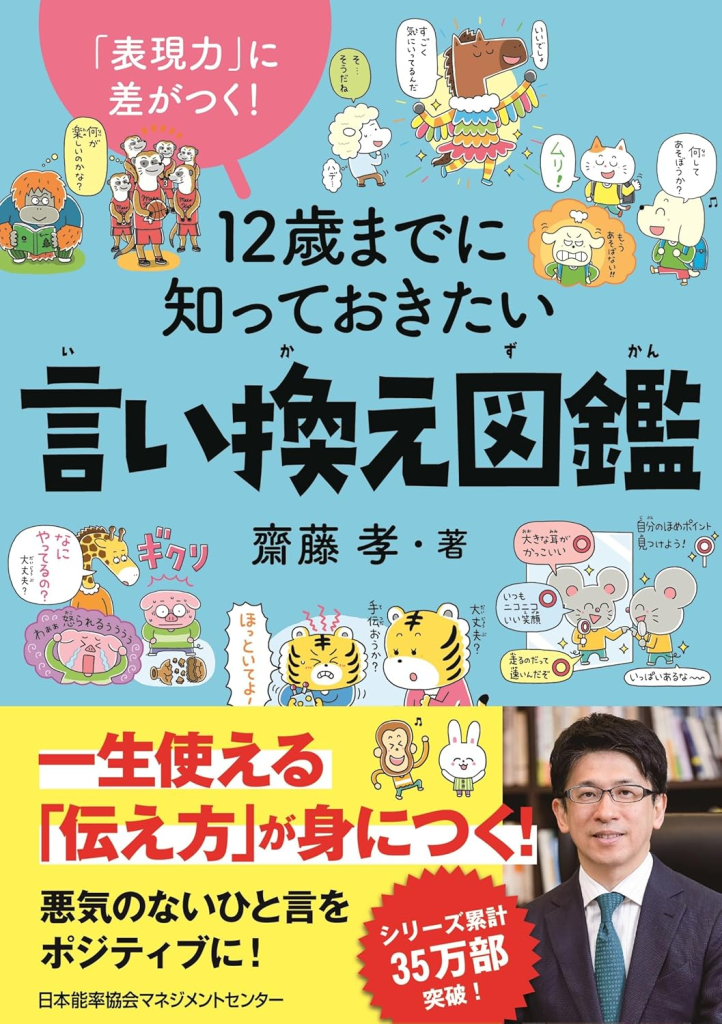
「表現力」に差がつく! 12歳までに知っておきたい言い換え図鑑
12歳どころか、もうすぐその4倍くらい生きてしまうわけなのだが、まだ間に合うよね?
いや、もう手遅れなのかもしれないけれど、それでもまだまだ社会人生活は続くわけで、対人だけでなく、自分自身に対してもポジティブな考え方を持ちたい。
そんな事もあって、ポチってみた。
似たような本に語彙力に関して書かれていたけれど、結局はこれも語彙力なので、そう考えるとこの人は似たようなテーマを何冊も書いていて大丈夫なのだろうか?とふと思った。
これがまさに余計な一言なのかもしれない
チームトポロジー 価値あるソフトウェアをすばやく届ける適応型組織設計
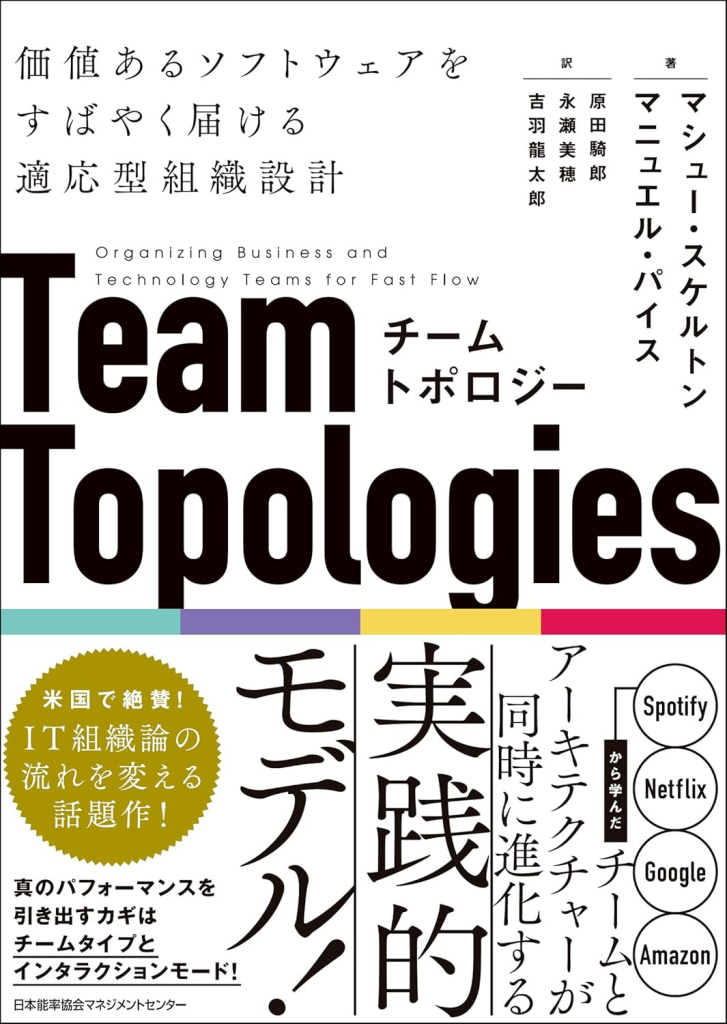
チームトポロジー 価値あるソフトウェアをすばやく届ける適応型組織設計
うーん、学んだ先がどこもものすごい大企業がラインナップされているのを見ると、「それって自社に本当に当てはめることってできるんだっけ?」がきになる一冊。
ともすると、さんざん世の中で出回っているものを寄せ集めました!みたいな一冊になってしまっていやしないだろうかと心配になるけれど、まずは読んでみようかと。
まとめ
199円という値段設定から考えると、各書とも何かしら一節でも役に立ったり心に残る言葉を得ることができれば十分元が取れるように感じる。
ただ、ランニング中に聞き流せるAudibleと違って書籍となるとやっぱり”読む”必要があるので必然的に時間をしっかり取る必要があるのは事実。
少しずつでも日々読み進めることができればと思う。
199円キャンペーンは9/4まで続いているようなので、掘り出し物がないかはもう少し眺めてみようかと思っています