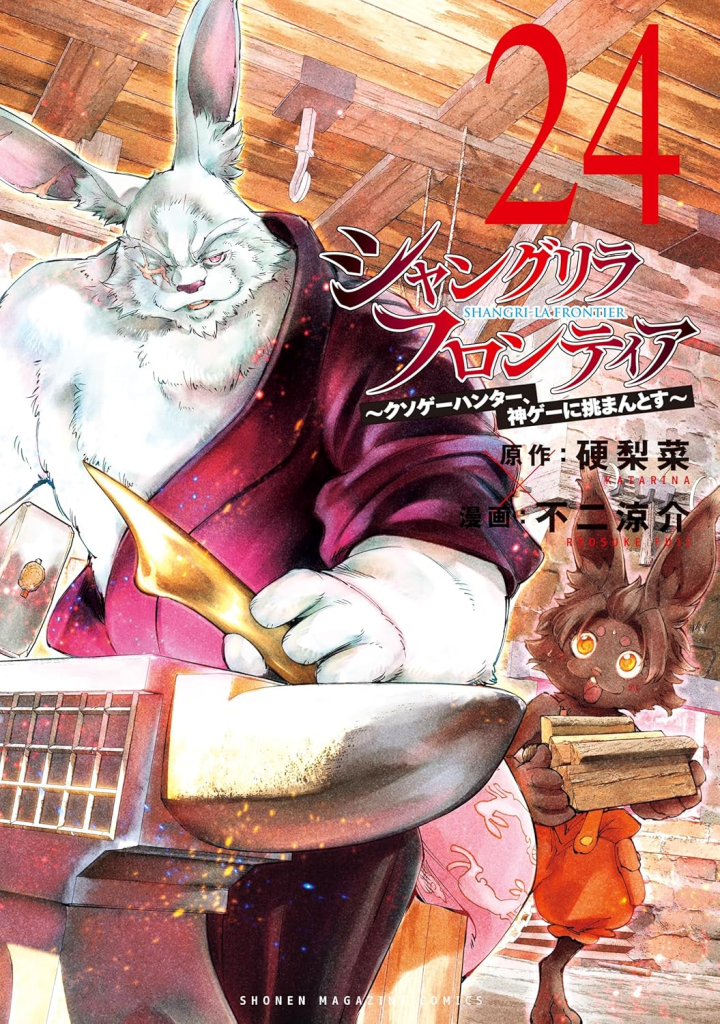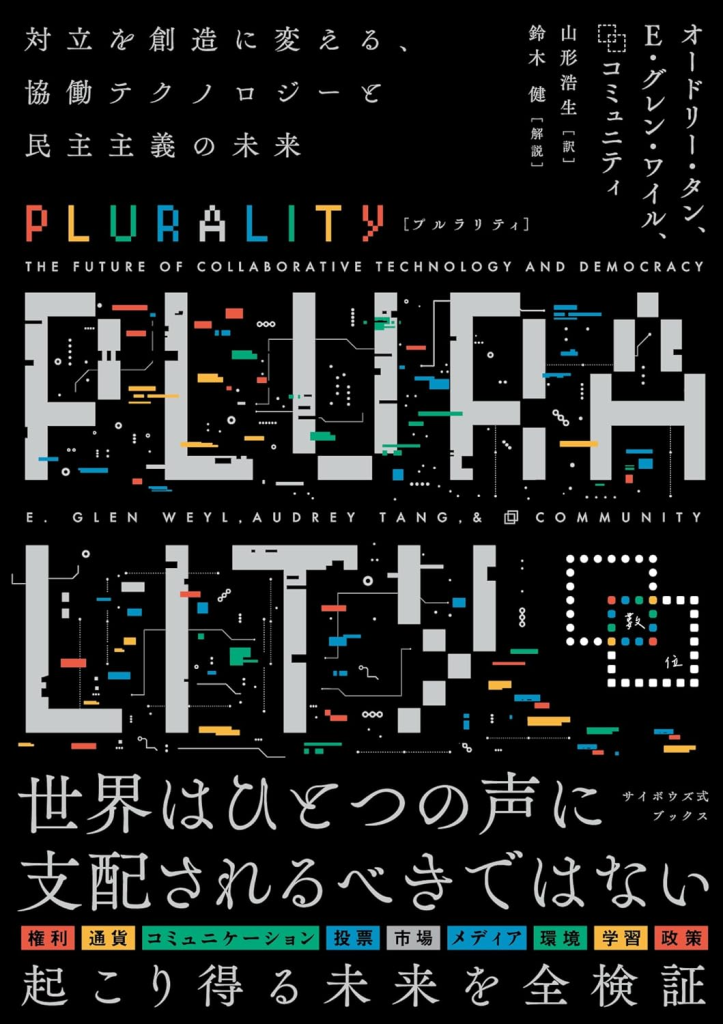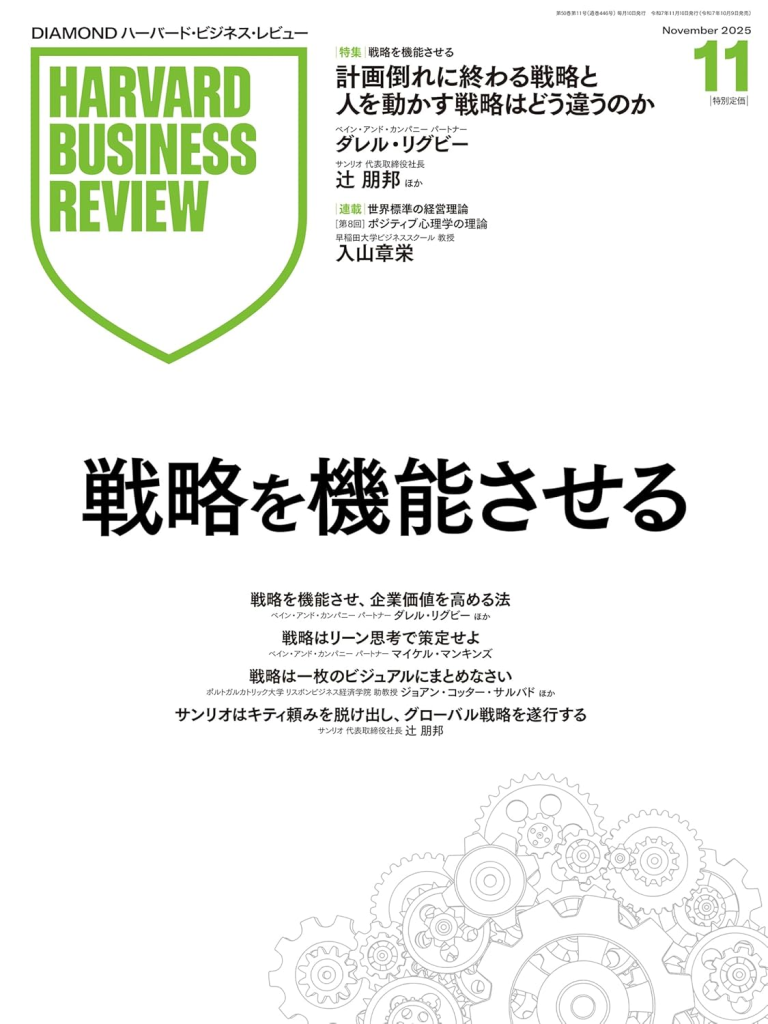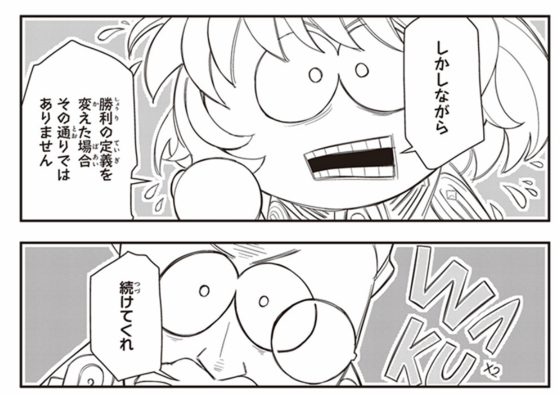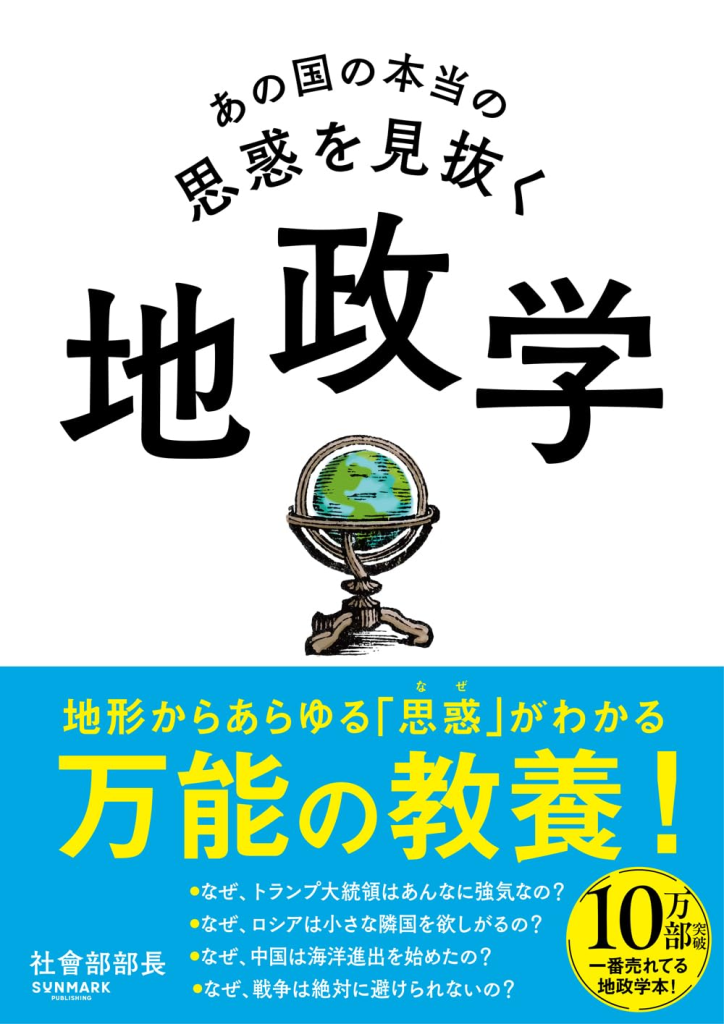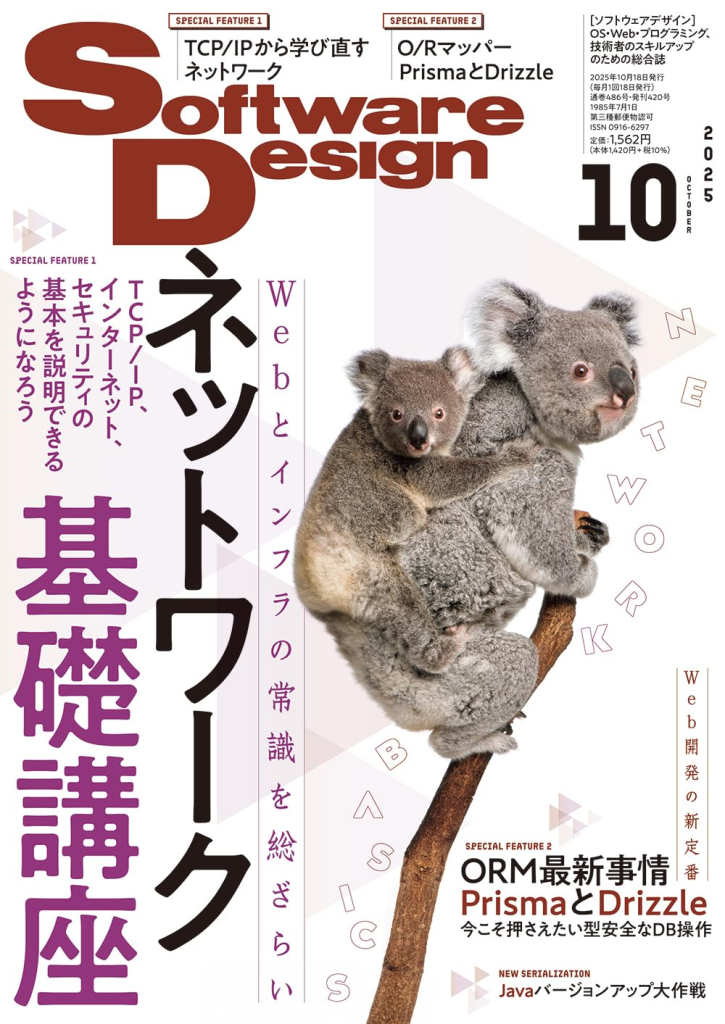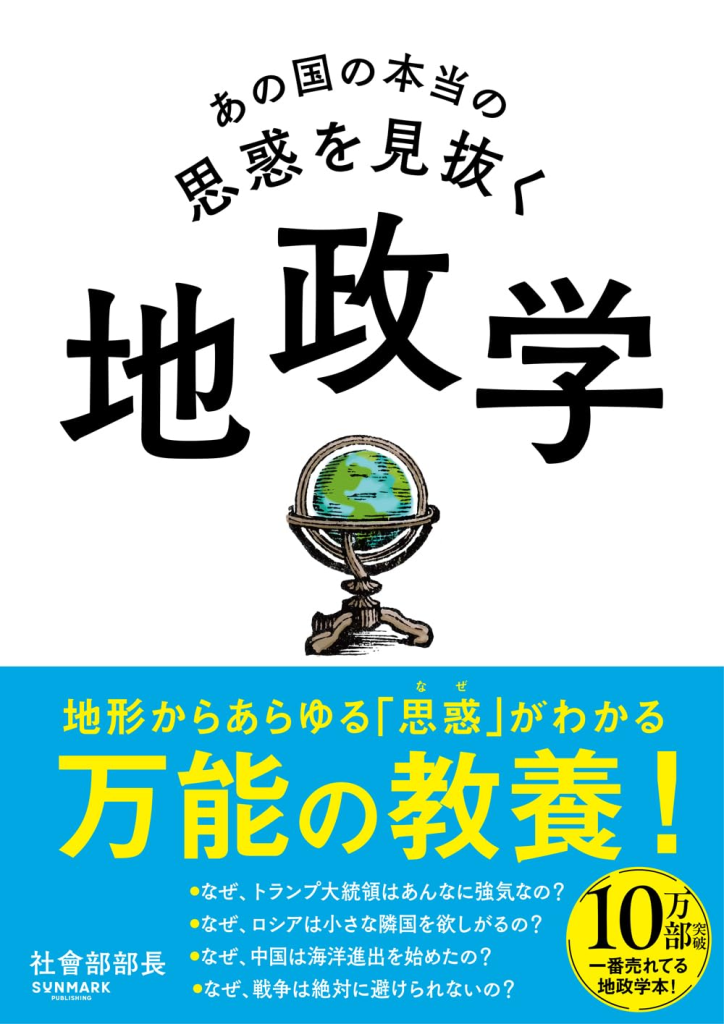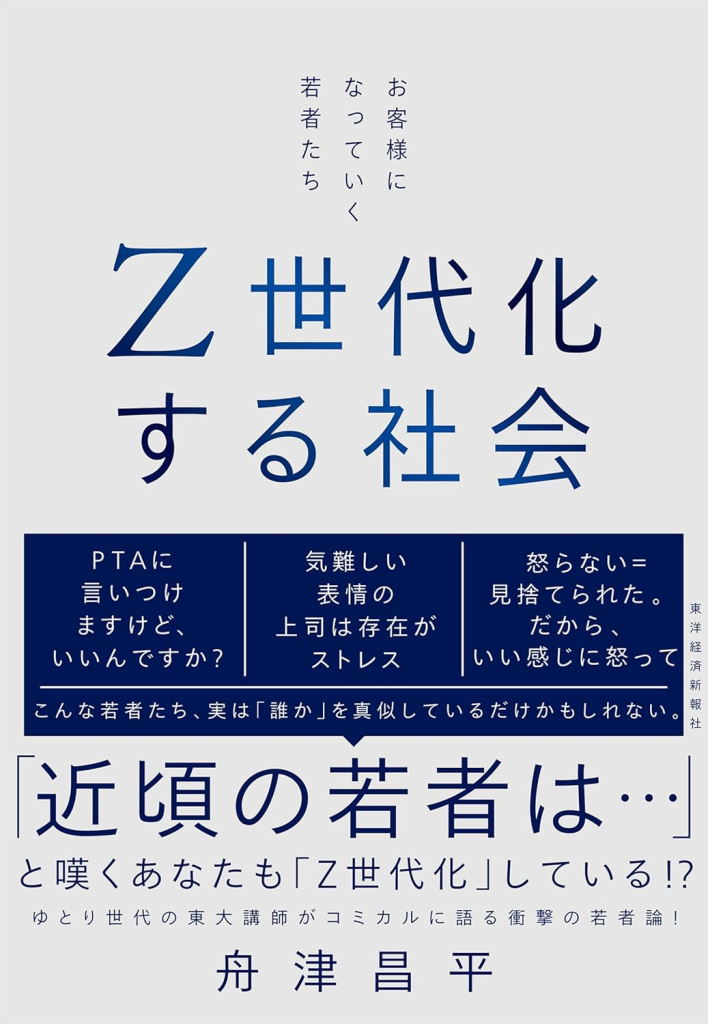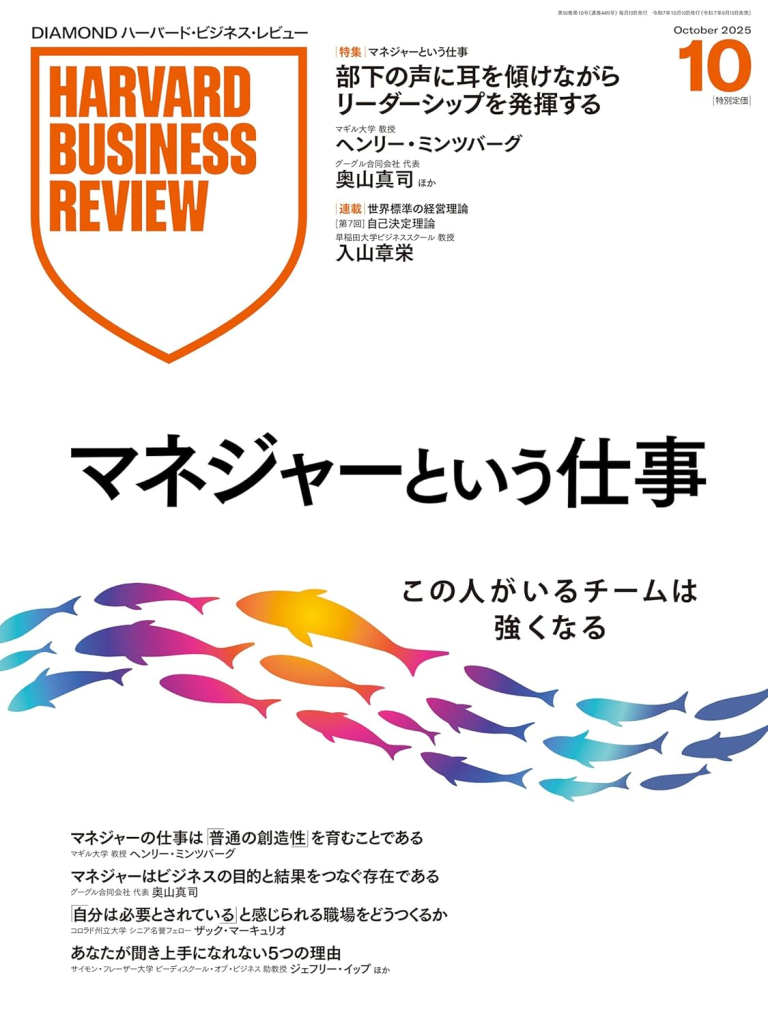今月もやってまいりましたSoftware Design。特集はネットワーク基礎講座です
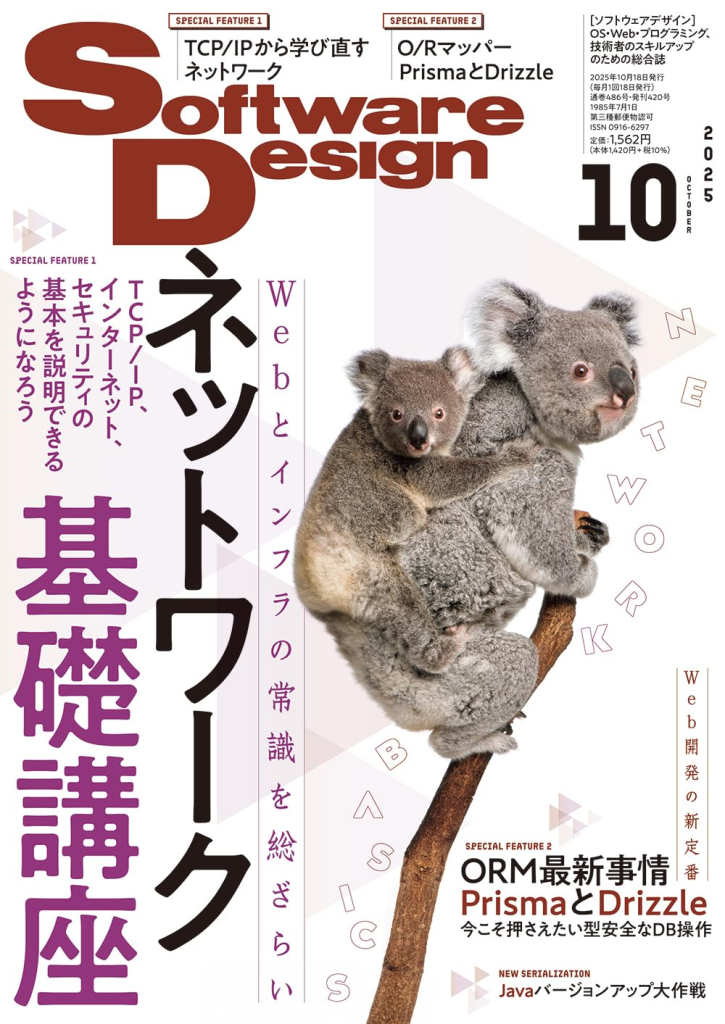
Software Design (ソフトウェアデザイン) 2025年10月号
ネットワーク基礎講座
普段、Webサービスやアプリなどを開発しているとこのあたりの必要性はあまり感じられないのが正直なところなのですが、定期的にこれら基礎技術に関しての特集を紙面ではやってくれます。
このあたりは、Software Design読者の層の広さを物語っているようにも感じます。
一方、普段は必要性を感じられないからと言って不要なのかというとそういうわけでもなく、稀にうまくいかないときにWiresharkなどでネットワークダンプを取って見たりすることもあるので、抑えておきたいところではあります。
何よりも、このあたりは多くの人が苦手とする部分なので、知っているとかっこいいです。
問題があったときに解析を行い、よくわからん呪文をブツブツと唱えながら解決していく姿はちょっと憧れますよね。
少し読むのは気持ち的に大変ですが、基本情報や応用情報を取得していない若手向けにも、定期的なインプットとして良いように改めて感じました。
ORM最新事情
正直言って、ORMは軽くしか使ったことがないんですよね。
自分自身がゴリゴリとコードを書いていたのは、それなりにパフォーマンスが要求される基幹システムだったので、SQLチューニングをOracleの設定と合わせてやっていました。
それを考えると、自動的にSQLを作ってくれるというのは、楽なようで実のところ問題を引き起こす種のような気がしてしょうがないですし、記事でもそのあたりはやはりORMの弱点として書かれています。
スキーマとの整合を自動で行ってくれるというのは、つまらないリリースミスみたいなものを防いでくれるという点でも非常に有用ではあるので、このあたりうまいこと解決してくれると良いのですが。
ORM側でSQLをうまく組み立ててくれることを期待するよりは、DB側のオプティマイザがより進化してくれることを期待する形なんでしょうね。
Oracleがルールベースからコストベースへ変わったときにも、ルールベースじゃないとパフォーマンスがでない!というシーンがあったように、使い所次第なのではないかと思いますし、その適用範囲が徐々に広がっていくのであればやはり抑えておきたいところではあります。
しかし、抑えておきたいところと言い出すと多すぎるんですよね。。
技術選定の舞台裏
連載2回目となる今回は、薬局DXを推進しているカケハシ社の事例です
サービス紹介 | 株式会社カケハシ – 日本の医療体験を、しなやかに。
この手の事例を実際のケースに沿った形で紹介してくれる本連載は、アーキテクチャを知るうえでも面白いですし、その時どきの事情みたいなものも垣間見れて良いです。
ただ、このあたりは膨大な背景、多岐にわたる選択肢がある中での技術選定となっているはずで、紙面が足りませんな。。。
もっとも、これ以上多くてもついていくのも大変なのですが。
自分自身が関わったことがないケースがやはり多いですし、”その当時はこうだったけど、今の状況からこう変えていきたい”という話を聞くことができるのはいいですね。
次回も楽しみにしていきたいです
次回
次回はAI開発ツールに関する特集が予定されています。
このあたりは流れがかなり早い分野なので、雑誌という形態でどこまでキャッチアップできるのかは若干不安ではあります。
その中でも、整理の仕方だとか観点だとか、どうまとめてくれるのか楽しみにしていきたいです