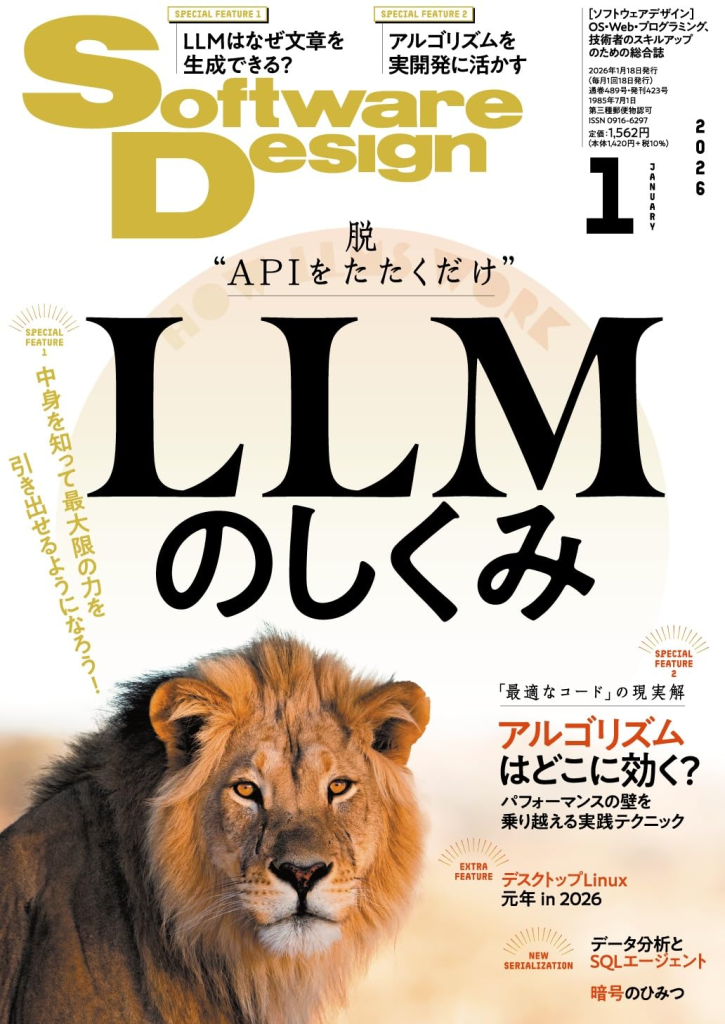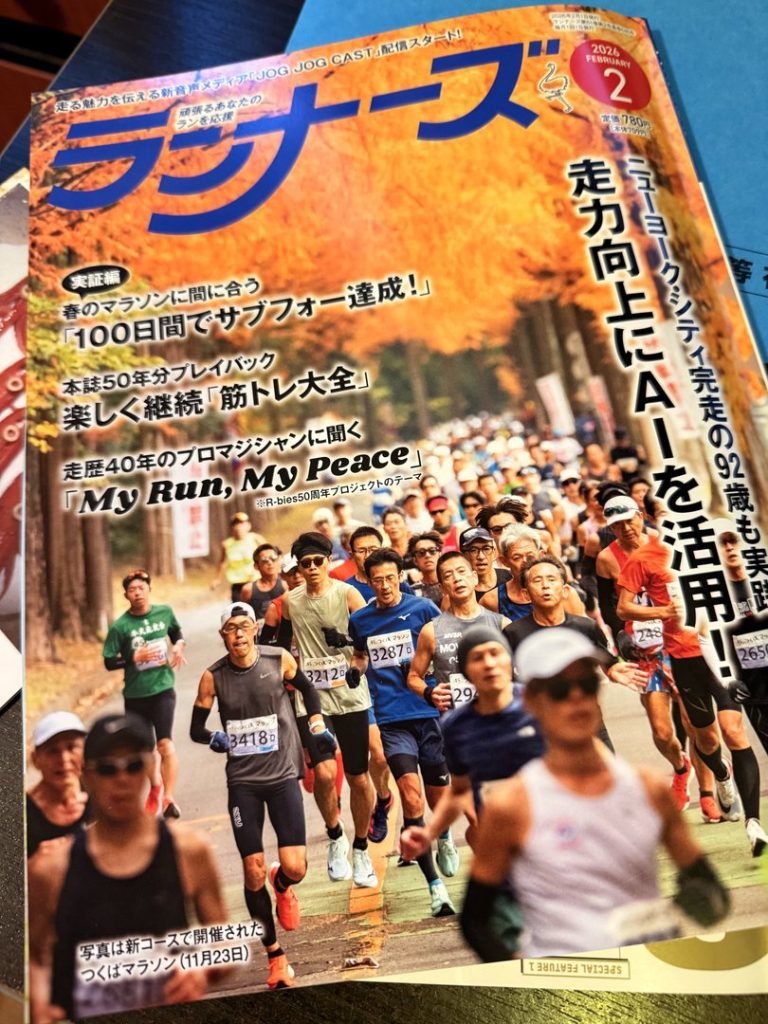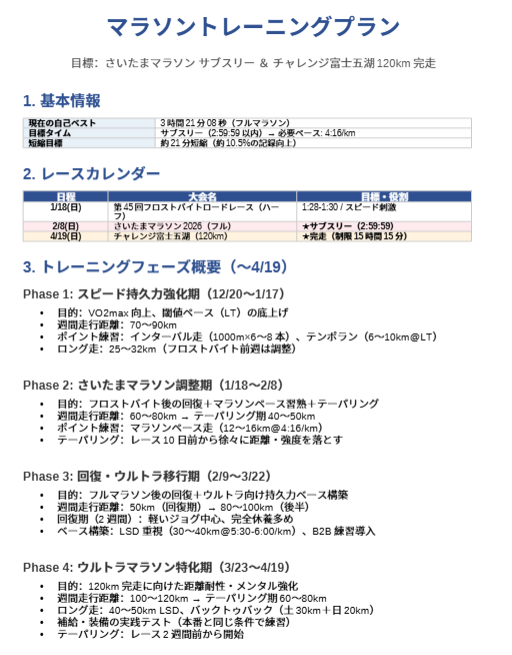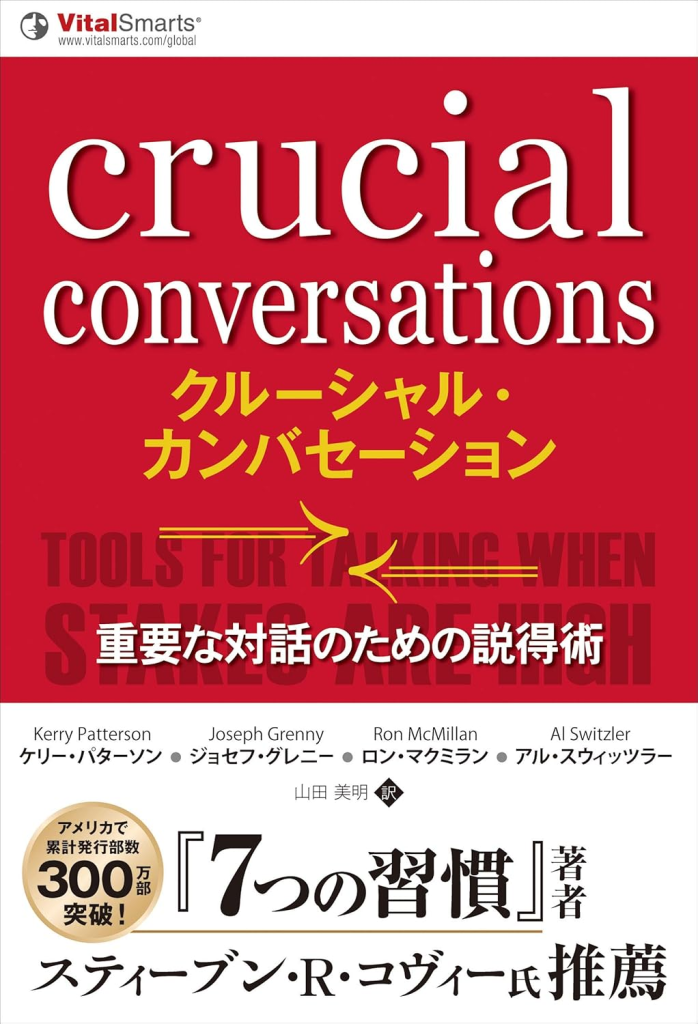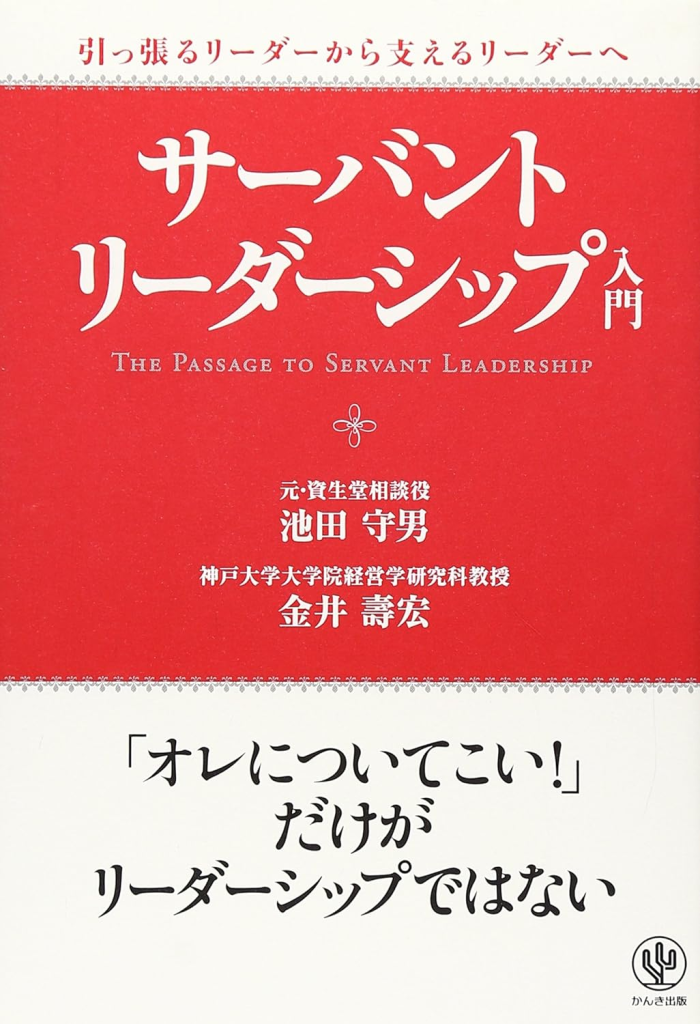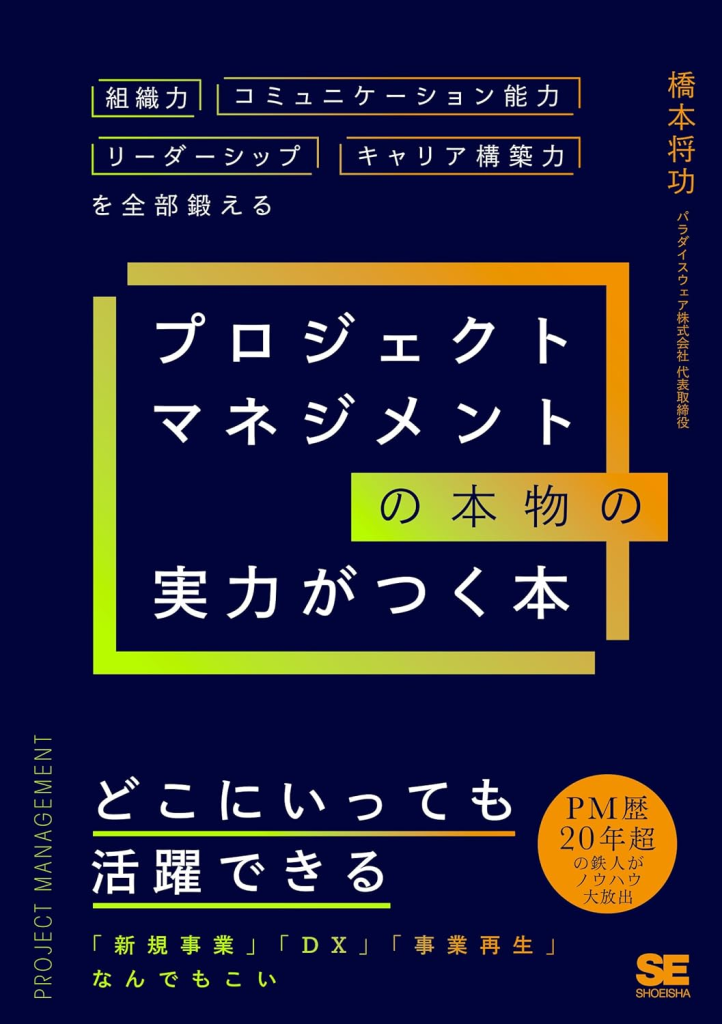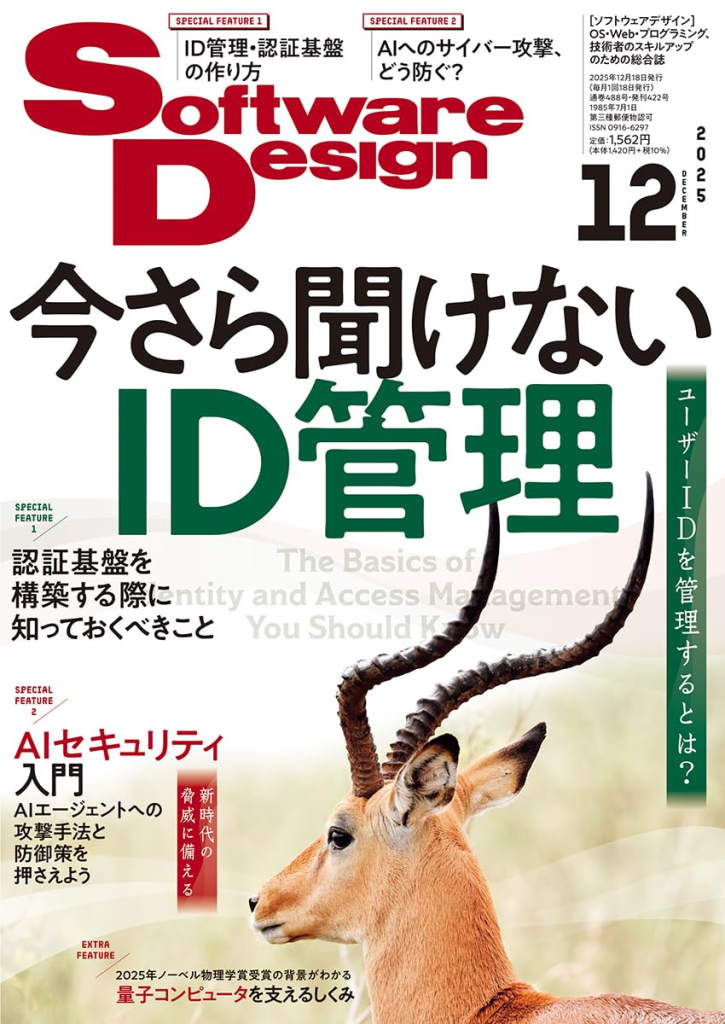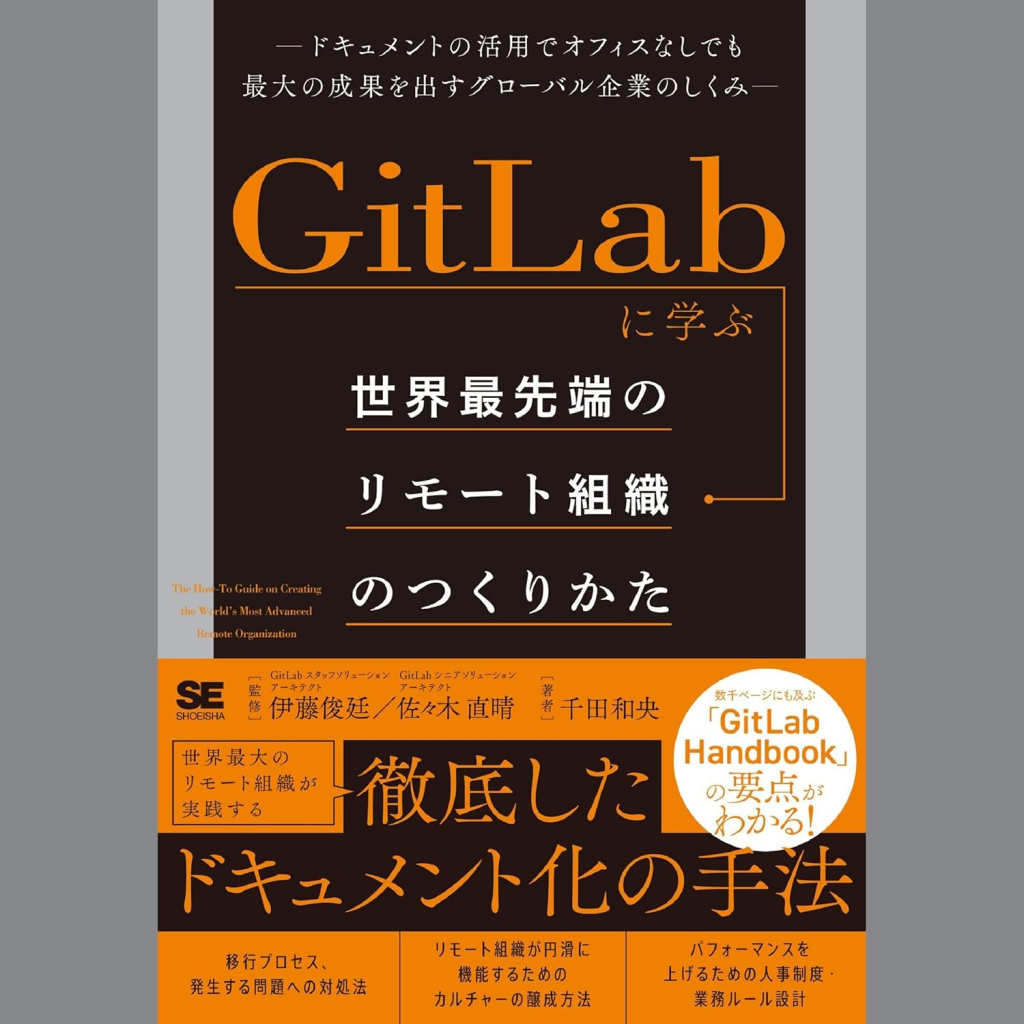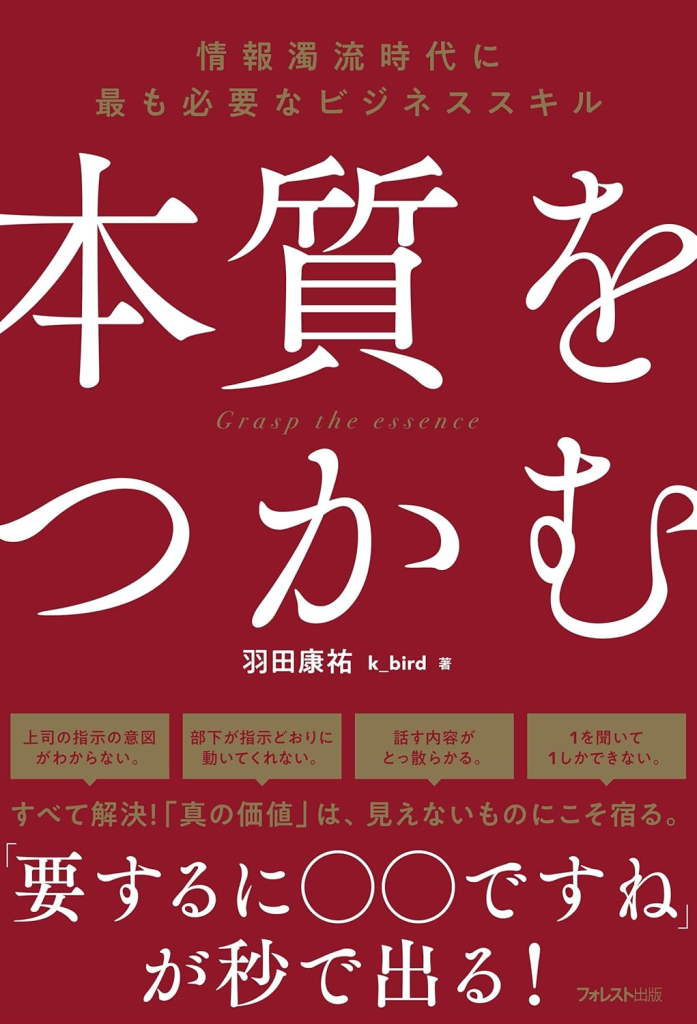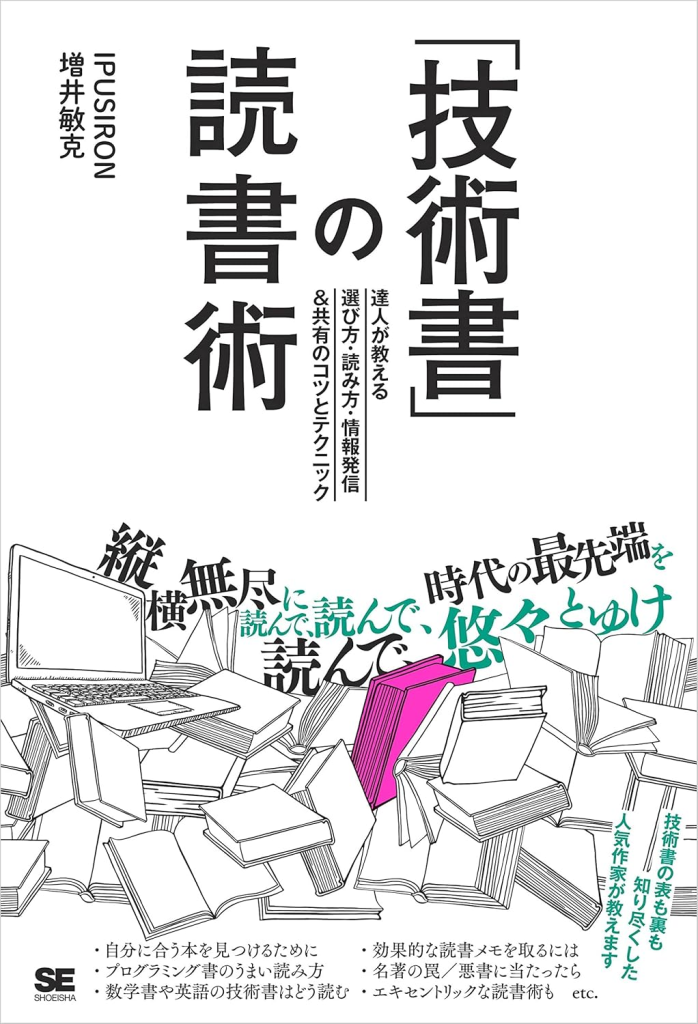なんとなく手に取った本だったが、自分自身が組織運営に関しては悩んでいるというか、なんとかしないとなと思っている背景もあり色々と考えさせられる本だった。
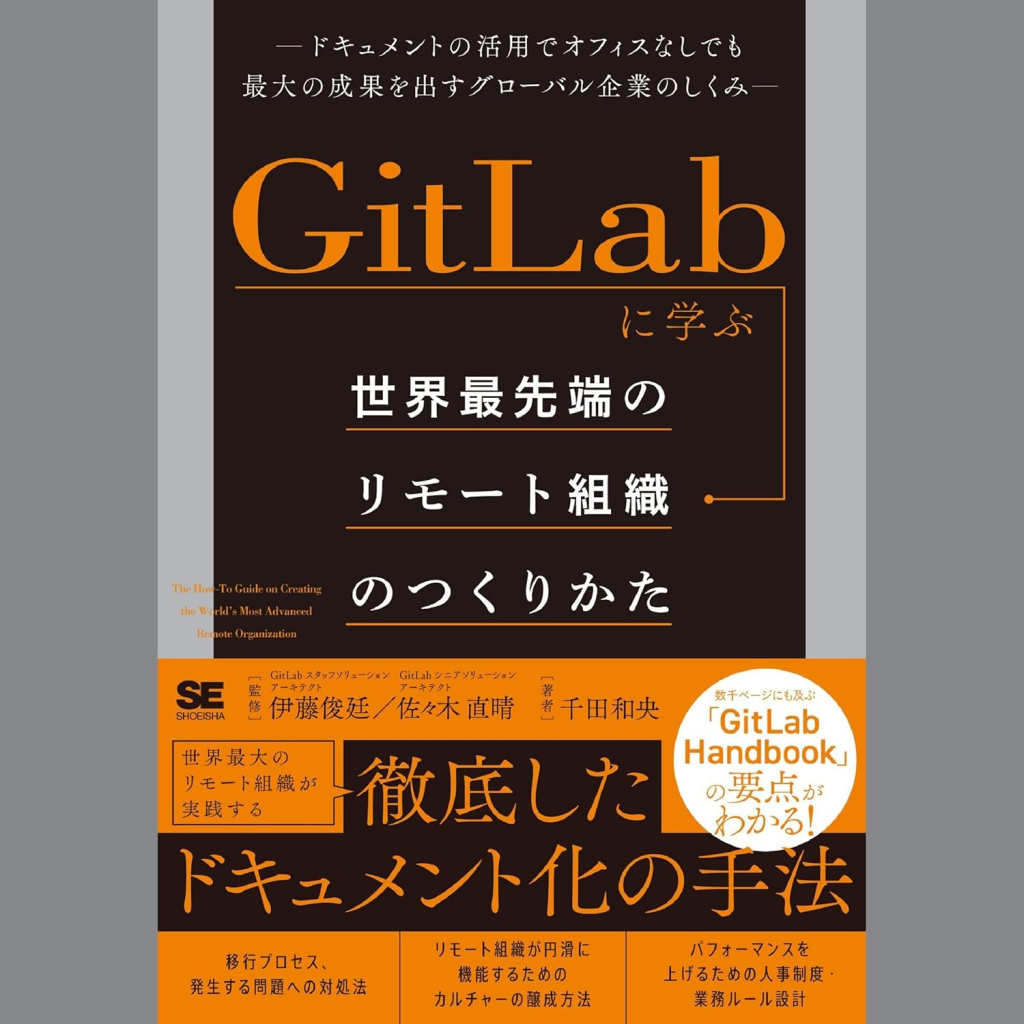
GitLabに学ぶ 世界最先端のリモート組織のつくりかた ドキュメントの活用でオフィスなしでも最大の成果を出すグローバル企業のしくみ
Audibleで10時間近かったけれど、2周してしまった
オフィスワーク、リモートワーク、ハイブリッドワーク
GitLabはタイトルの通り、全従業員がリモートワークを実施しているオールリモートの組織とのこと。
本書としては、リモートワークの推進。それもハイブリッドの形態ではなくGitLabと同様に全従業員をリモートワークにすることを推奨としている
ただ、個人的には少し極端な気もする。
ハイブリッドの問題として挙げられているのは、オフィスワーカーとリモートワーカーそれぞれのメリット・デメリットによるお互いへの不満から来ているもの。
オフィスワーカーにとっては、通勤時間があることへの不満はありつつもオフィス設備の利用や情報取得の即時性。特に会社組織の上位レイヤーが出社している場合は、それらの人たちからの覚えの良さや情報伝達のスピードが利点として挙げられる。
リモートワーカーはなんといっても通勤が無いことによる時間の有効活用が一番の利点となる。一方で、オフィスワーカーだけが享受できる設備や情報取得に対する格差を感じてしまうところかもしれない。
先輩社員が出社している場合は、直接的な指導を受けやすいのは間違いなくオフィスであるだろう。
実際問題、新入社員やロースキルの若手メンバー育成を考えた場合、オフィスワークのほうが質問のしやすさや、問題を抱えていることへの察知のしやすさという点で良いように感じる。
どうしても、こういう有名企業の場合は、そもそもそこに入ってくる人のベースが高いという前提があるのではないかと勘ぐってしまう。
このあたりは、単純に管理の仕方の問題はあるかもしれないが、正直できる気がしないのが実情。
結果として、これを実現するためには先輩社員も出社をする必要があるなど、全体的にリモートから逆行してしまうという問題が生じる。
GitLabをオールリモートで効率的な組織足らしめている一つの要素として、情報を徹底的にドキュメント化していることを本書では紹介している。
このドキュメント化ができるのであれば、ハイブリッド状態でもある程度まで情報格差は解消できるのではないかとも思う。
オフィスワークするかリモートワークをするかの選択肢がエンジニア側に委ねられているのであれば、そこまで問題にならないのではないだろうか。もちろん、このドキュメント化の徹底ということの難しさは大いに感じることではあるのだけれど。
ドキュメント化
本書を読み、そしてGitLab Handbook の存在を知ってから、自社のドキュメント化をなんとか進めないといけないという認識を強く持つようになった。
あまりにも暗黙のルールが多すぎてしまい、ルールが定まっていない。
もしくは、明確になってなくその時その時で判断されてしまっている。これは臨機応変とは違うだろう、と。
リモートワークをするためではなく、しっかりとしたルールを明確化する。記録を取るということはこの先のAI活用が当たり前となる会社組織の中で非常に重要な要素に感じる。
ツールの進化によってドキュメント化も随分と以前と比べればやりやすくなっている。
特に私はミーティング中に話に夢中になってしまってあまりメモを取ることが出来ない。自動文字起こしをしっかりと活用しつつ、そのテキストをどう活用していくのかを含めて検討し、明文化していくことで組織の中での浸透を図っていかなければいけない
うーん、現状があまりにも出来ていないのでやることが多すぎてめまいがしてくる
これまでは正直、そのあたりをバックオフィス部隊の仕事であろうと文句をいうだけの立場だったが、少なからずメンバーからの質問は定期的に発生する。
それを考えると、二度手間なところはあるが、整備したほうが全体としては良くなりそうな気もする。
一方で、それはあくまで暗黙のルールで、公式的に明文化されていないのであればそれを明文化する方に組織内へ働きかけるのが正攻法ではある。
正攻法ではあるのはわかるんだけれど、結果としてすごく面倒くさい方向になりそうな気もするので気が進まないというのも正直なところ。
まとめ
読んでいて、学びになることは非常に多かったのだけど、モヤモヤしていたりだめだなーって思うところが多く、「ではどうするか」に関しては足がすくむところはある
言ってしまうと、本書で書かれていることの殆どは、会社組織における人事制度を中心とした枠組み。
開発組織に属している中で、どこまで独自制度を整備できるかということには結構な制約がかかる。
そして全社的な立場に立ってしまえば良いのかもしれないけれど、それは別にやりたいことじゃないんだよなーって。
まずは自組織でできるところ。
特にドキュメント化に関しては進めていくとしてそれ以上の範囲をどうするかは戦略を考えないと行けない。
今回、本の主題であったリモートワークに関して記事を書いたが、それ以外にも初めて聞く単語や考えさせられること満載の書籍だった。
GitLab Handbookは公開されていることなので、膨大ではあるが少しずつ読み込んでいってエッセンスを有効活用していきたい。
いい本だった。