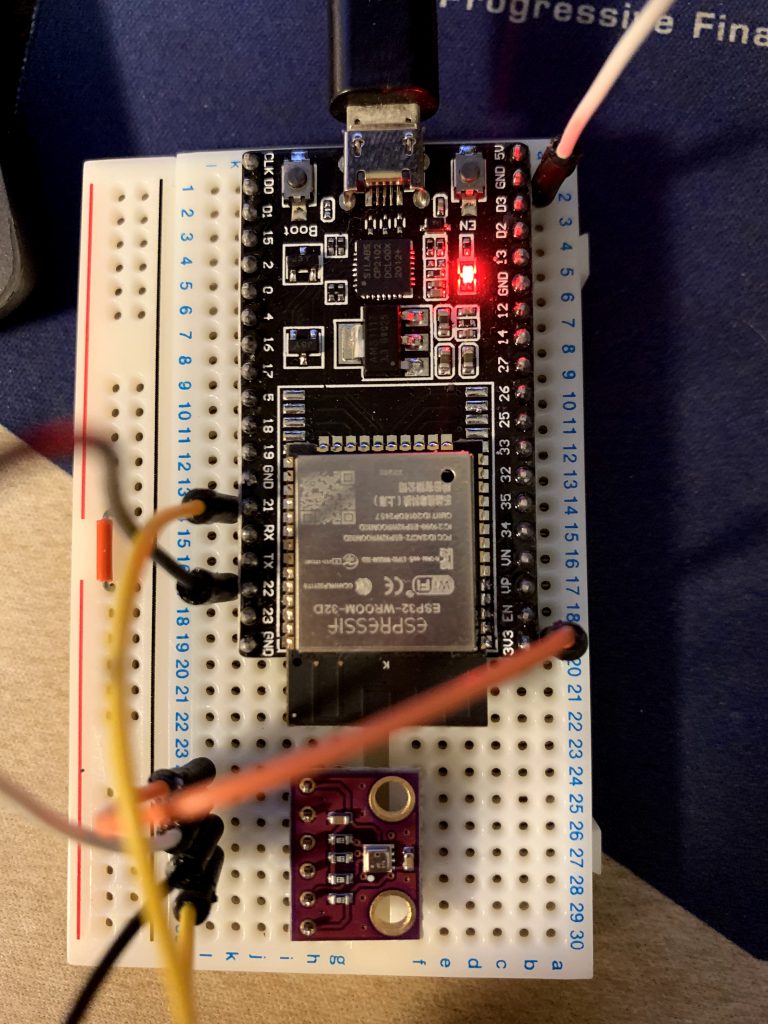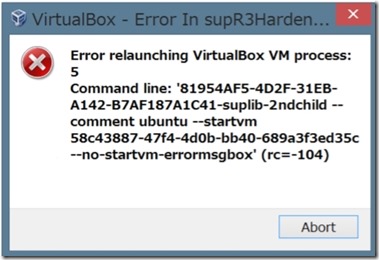AWS Summit Tokyo が6/2-3の日程で品川プリンスにて開催されていました。

AWS Summit Tokyo 2015 クラウドで、未来を「今」に。
http://www.awssummit.tokyo/
仕事の関係で、Day1の午後のみの参加となってしまいましたが感じたこと・考えたことのメモをば。
前提
AWS自体を私が触り始めたのはつい最近で、まだ1年程度。
しかも、触り始めたといってもずーっと何かをしているわけではなく、EC2とRDSを少し触りながら既存システムのAWS環境での動作確認等を行った程度のレベルなのでたかが知れます。
AWS Summit は初参戦で、申し込みが遅れてしまったのでほとんどのセッションが満席><
実際には事前のセッション申し込みはチェックされなかったので意味がなかったっぽいけれど・・・。
[Dev-01]デベロッパー視点で見たAWS
AWSの各種サービスに関してのお話。
CodeZineで連載された、アプリ制作に関する話も交えながら、数あるサービスの中でどういったものを使っているのか?など。
ちなみに連載は見ていなかったけれど、こちらが初回。
【制作1日目】 池澤あやかさん、イベント会場がヒートアップ間違いなしのアプリを制作、まずはクライアント側処理です ~ Amazon S3 / Cognito / Kinesis / DynamoDB 登場
http://codezine.jp/article/detail/8642
S3の使い方や、Cognito。それにLambdaの話などが目につきました。
また、私の現在の業務からはちょっと考えづらいですが、AWSを前提としたアプリケーションを作る場合に、
ローカルでの開発(オフライン状態)が難しいという話は少し新鮮に感じました。
開発環境をそもそもクラウド等に構築するようなこともあると思う。
今後の開発のあり方というものは少し見守っていく必要がありそうだなぁ。
[Dev-02]デベロッパーが切り拓く、次の時代
タイトルからもわかるように、AWSと結局全然関係ないような内容だった。
パネリストはみんな大好きnaoyaさんと大場さん。
開発者はどういうスタンスで次の時代を乗り切っていくのかという話。
ともすると、どうしても技術オタクになってしまいがちな人が多いけれど、
技術が先にあるのではなく、課題が先にあって、その解決の手段として技術がある。
何かの技術に対して掘り下げていくことは悪いことではないんだけど、それをキャリアとして計画するのはどうなのか。
出来ないことを解決するためにいろいろな試行錯誤があるわけで、その前提条件として何らかの技術をおいてしまうと
出来ることや成長にブレーキがかかってしまう。
この話は、今一度自分自身を思い返したいところだと思いました。
そういう意味でも、最後にnaoyaさんが話をされていましたが、自分のポジションをちゃんと把握することが大事。
そのためには、現在の周りの状況が見えている必要がある。
我々エンジニアは、結局のところ死ぬまで勉強が続くのであるのだ。
[KEY-03]DevCon Day1 クロージングキーノート:2035年、その時デベロッパーはどう生きるか
大前さん親子の会話。
大局観的なとらえ方は面白いと思いつつも、少し気になるシアターセッションもあったので途中退席。
後でセッション資料や感想を確認したいところです。
それにしても、茶の間での会話レベルが高いな~。
わが家でもそういう話をするような時代が来るのかな?
まだまだ小さいわが子を見ていると、少し想像できませんね。
ちなみに、期待していたシアターセッションはあまり面白くありませんでしたので割愛。
[TE-05]ファイヤーサイドチャット~エンタープライズ企業はいかにクラウド化の流れを進めるべきか~
Amazonのえらーい人3人を交えたトーク。
ちなみにファイヤーサイドチャットというのは、暖炉のそばで話すようにフランクな会話ということらしい。
お題としてはエンタープライズ企業におけるクラウド化に関して。
実際のところ、AWSはすごいメジャーになってきていると思っているんだけど、日本の企業のどの程度がそう思っているのだろう。
AWSのようなスモールスタートが出来る環境であれば、大企業じゃなくても活用できるはずなんだろうけれど、
たぶん多くの企業ではそういうところまで目を向けていないんじゃないかな~。
印象に残った言葉としてはこれ
問題はテクノロジー側にあるのではなく、組織の文化だったりする。 口では色々なことをいうことは出来るんだけど、実際に動くことが出来るのか。
はたして、日本の企業はそういう考えを持つことが出来るのか。
個人的には、そういう考えを持てないと今後は生き残れないくらいまで過激なことは言わないけれど、
いいものはどんどんと活用していけばいいと思うんだよね。
ベンダーロックインという考え方は確かにあって、AWSがなくなったらどうするんだ?というのはリスクとしてはわかる。
その時には作り直せばいいんだ!って軽々しく口に出してはいけないことも、まぁわかる。
ただ、その時が来るまでに生き残れるのか?ということを考えるのであればやっぱりスピード感を持ってことにあたらないといけないと思う。
やはり、最後はいつも人の問題になるんだな。
実はこのセッションはこれ以外にもすごい色々なことを考えさせられるセッションでした。
AWSを使うことによるメリットを、どうエンタープライズに伝えていくのか。
実は業務でも少しかかわっている課題でもあるので、より深堀しながら考えて進めていきたいところです。
シアターセッション
展示会場に設置されたシアターセッションも時間のあいまではありますが、少し拝見させていただきました。
各回ともに10分程度の時間なので、それほど多くの情報は得られませんでしたが。
スカイアーチネットワークスさんがchef やserverspec。Zabbix等をまとめたツールに関しての話をしていた。
DevOpsサービス (スカイアーチネットワークス)
http://www.skyarch.net/devops/
chef や serverspec に関しては、知ってはいるものの、Windows主体で私が動いている&それらのツールがWindowsではイマイチ使いづらい印象が結構前にはあって、
本格的に見ていませんでしたが、もうそろそろ見直してみようかな~と。
まとめ
見てわかる通り、申し込みが遅れたこともあって「AWSを使いこんだぜ!」っていうセッションにいけませんでした。
どちらかというと、開発者や企業が今後どういう形で進めるべきか?というような、AWSべったりではないセッションが多かったです。
個人的には、それがとても良かったように感じます。
特に、ファイヤーサイドチャットで得たことは、今後大きな糧となってくれると思っています。
セッション資料等に関してはきっとAWS公式がまとめて公開してくれると勝手に思っているので、
AWSを使い倒したぜ!みたいなものに関しても見ていきたいと思っています。
今後が楽しみです!