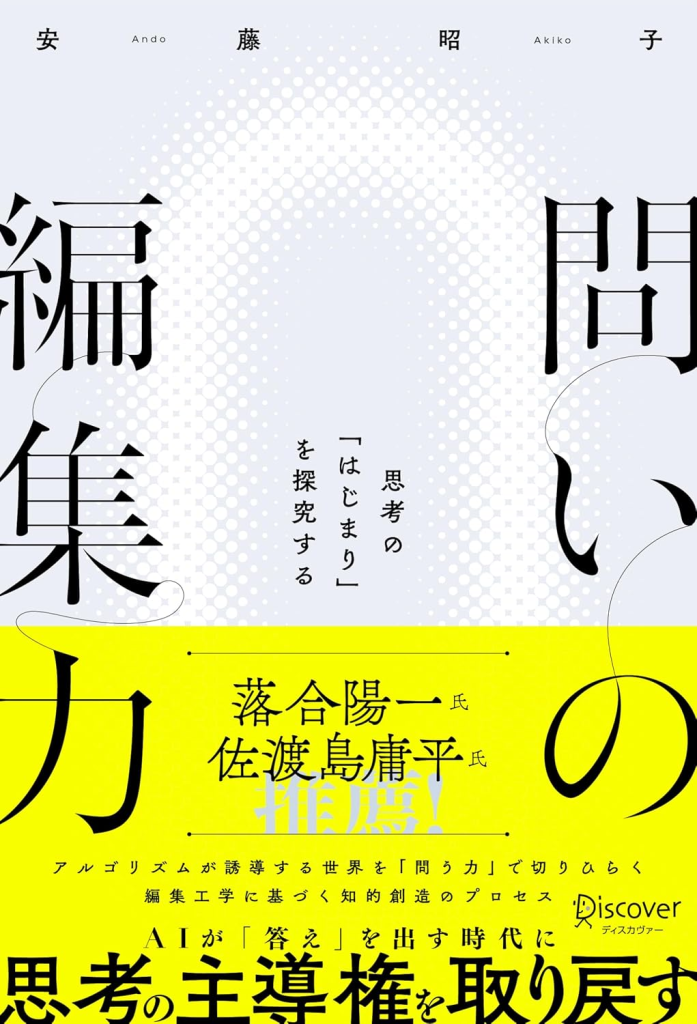安藤昭子著「問の編集力」を読んだ
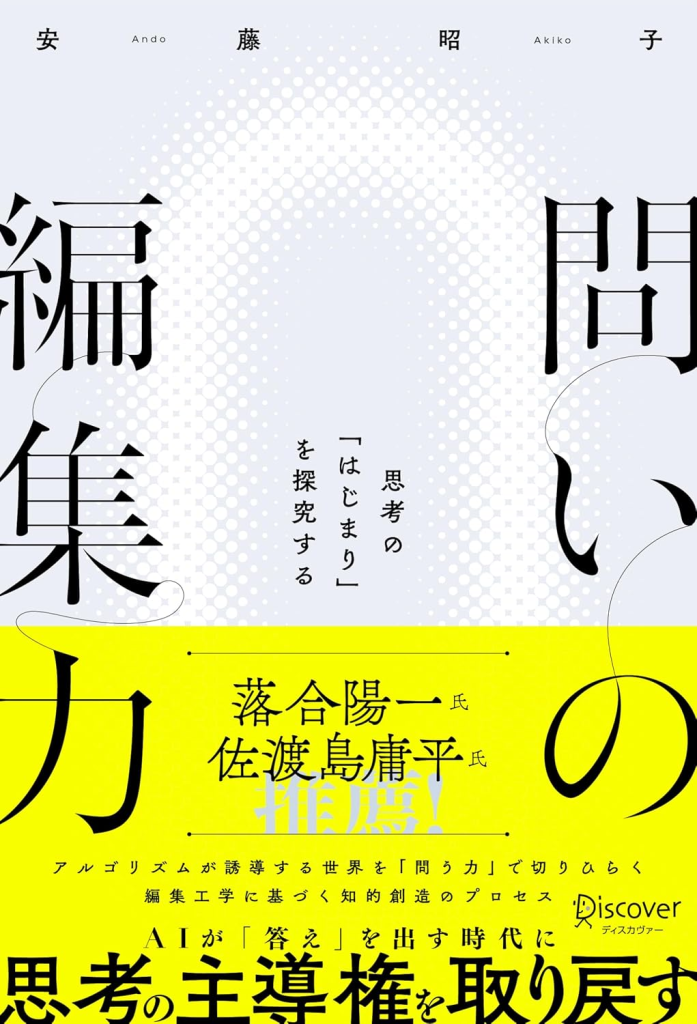
”問う”ということはどういうことなのか。
物事を探求しようとしたときに、一番最初に現れるべき”問い”というものに対して。解決方法ではなく、”問い”そのものに対してフォーカスして書かれている本だと認識しています。
つまり、解決策を導き出すようなハウツー本ではなく、どちらかと言うと哲学的な印象を受けました。
私たちは日々生活しているわけですが、その普段の中で当たり前としているものにもいたるところに”問う”事のできる事柄がある。
読書にしても、その読書行為は本当に「読む」という能動的な行為になっているのか。安藤昭子氏の「問の編集力」は、そんな私たちの行為そのものに一石を投じる一冊です。
「問い」を育む土壌としての好奇心
著者が強調するのは、子どもたちが持つような純粋な好奇心の大切さです。日常の中の「当たり前」に疑問を投げかけ、そこに潜む驚きを見出す能力。この感性こそが、「問い」を生み出す源泉となります。
私にも、1歳になる娘がいますが本当にいろいろなものに興味を持ちます。
そしていたずらします。
しかし、大人から見ればいたずらでも当の本人としては真剣そのもの。彼女を突き動かす好奇心は、やはりおとなになるに連れ身につけてしまった”当たり前”によってわからなくなってしまっている。
随分とつまらないおとなになってしまったなぁと、今更ながらに思ってしまうわけです。
ネガティブフィードバックの意義
問いとは何なのか。
本書で出てくる一つの答えは、立ち止まり考えることなのかと思っています。
現代社会では常に「前に進む」ことが求められがちですが、本書は敢えて立ち止まり、現状に問いを投げかける「ネガティブフィードバック」の重要性を説いています。この視点は、私たちの思考や学びのあり方に新たな示唆を与えてくれます。
まとめ:問いの力が開く新しい世界
本書は、単なる読書術や思考法の本ではありません。それは、私たちの中に眠る「問う力」を呼び覚まし、世界との新しい関係性を築くための哲学書とも言えます。日常の中で「問い」を育み、それを通じて世界を新しい目で見る。その実践的な方法論を、本書は静かに、しかし力強く提示しているのです。
一方で、何を問うべきなのか?も合わせて持たなければ有限な時間の中であらゆることに好奇心を持っては生きていけないわけで。
とはいえ、また当たり前として扱って問いを投げかけることに臆病になっていってしまわないようにしていかなければいけませんね