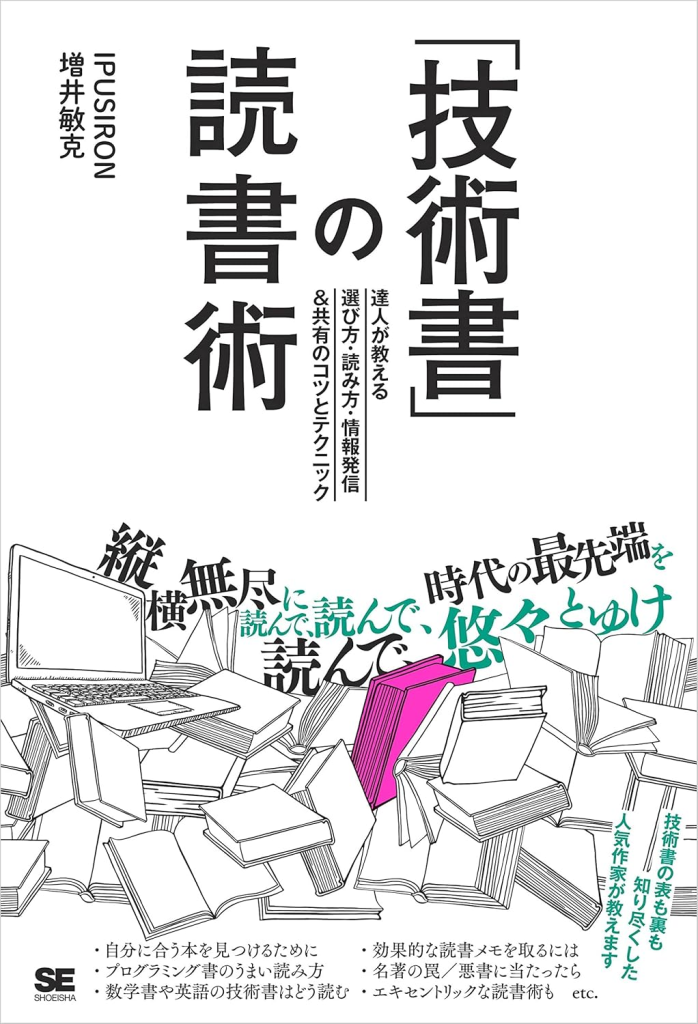
技術書」の読書術 達人が教える選び方・読み方・情報発信&共有のコツとテクニック
読書術と銘打たれているが、読書の方法にとどまらず、本の選び方から始まり、読み方。そして情報発信や共有の方法までを含めた構成になっている。
選び方に関しては、書店や図書館での選び方は正直私にとってはあまり活用することはないかな?と思ったが、洋書を買う際のHumble Bundle, Better World Booksなどは初耳でした。
ちなみに、紹介されていたBookDepositoryはすでに閉鎖されているそうです。。。
特にHumble Bundleは、1.0USDでのまとめ買いもできるみたいで、その時々でラインナップの差はあるのですが試してみるのには面白そう。
洋書の場合は読むのが大変そうという問題はあるのですが、このあたりはLLMを駆使するなりしてなんとかしていきたいところですね。
Humble BundleはPDFでの提供をしてくれそうなのでまだなんとかなるのですが、問題はKindleでの洋書です。
Kindleで購入して読み進められていない本も実は手元にあったりするので。。。
そういう意味で考えると、Amazonで洋書を買うのはやめておいたほうが良いかな、という気がしてきてしまいます。
Kindleで読みたければPDFを取り込めば良かったと思うので。
読み方に関しても、わかっていながら実践できていないことが多いです。
特に、物理本であればパラパラとめくるということはよくあるのですが、電子書籍になるとパラパラと進めるのが正直難しいんですよね。
ただ、技術書などで例題をコーディングするような系統だとどうしても時間がかかり、結果として最後まで走り切ることが出来ないケースがよくあります。
そういうときに、定期的に先を見ることで、進めるためのモチベーションを復活させるということはいいな、と改めて感じました。
このあたりは実践していきたいところ。
本を読んだあと。
基本的に私はBlogに書くことにしているけれど、書いているだけだな、と改めて思った。
あまり活かしきれていない。
仕事におけるコミュニケーションは、すべからく行動に結びつく必要があるということをどこかで読んだ気がする。
本に関してもそうであって、この本を読んだ後で、では自分の行動として何に活かしていくのか。どう変えていくのか(場合によっては何も変わらないこともあるとは思うけれど)
つまりは何かしらの学びがあってほしいところ。
その整理ができていないのだと思った。
まずは、Blogに書く前にObsidianに記載してその内容を整理可能にする。
そしてこの本を受けてどうしていくのかを考えて見るということをやってみようと思った。
洋書に関しての挑戦もしていくとともに、技術書を継続して続けるためにも定期的に先を見てモチベーションを上げる。先を見てモチベーションが上がらないようであれば、それは逆にあまり現時点の自分にとってはタイミングとしてあっていない本なのかもしれない。
その時はおいておこう。
また、新しいプログラミング言語などを学ぶ際には図書館で複数冊借りて違いを見るというのも面白い方法だと思った。これは直近でDartを勉強しようとしているので試してみたいところ。
ただ、千葉市の図書館でFlutterを検索したら3年前のSoftware Designしか出てこなかった。。。

技術書はなかなか厳しいな。現実は。。
これは、都内の図書館のほうが良いのかもしれない